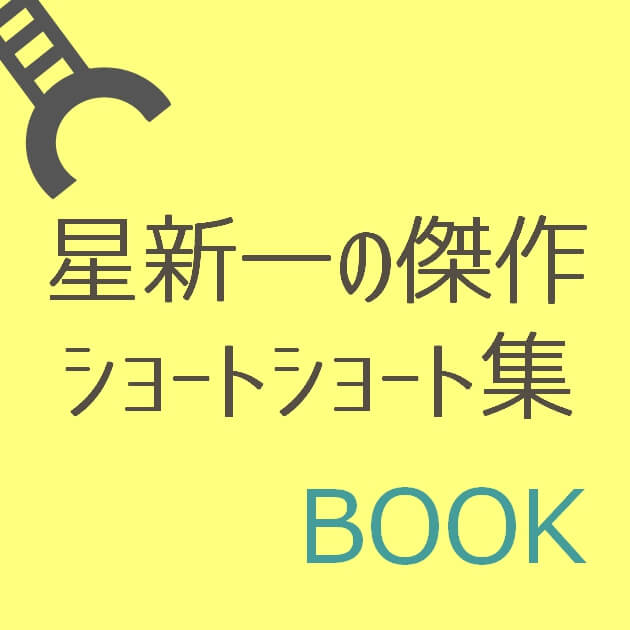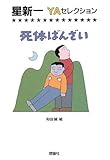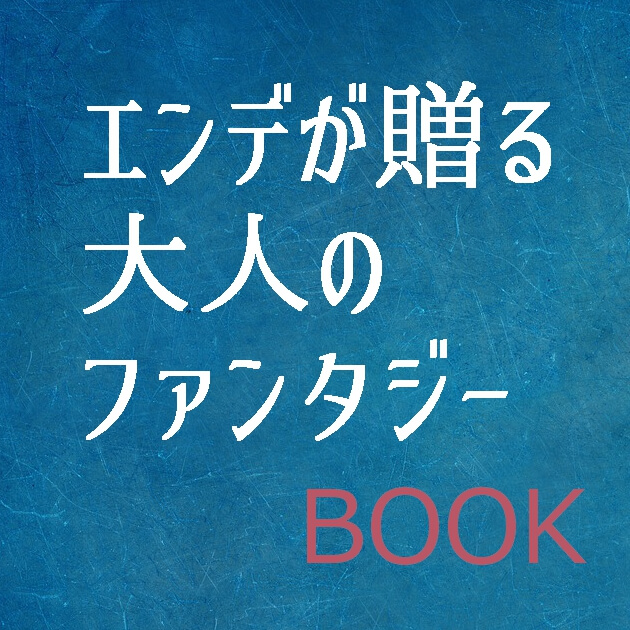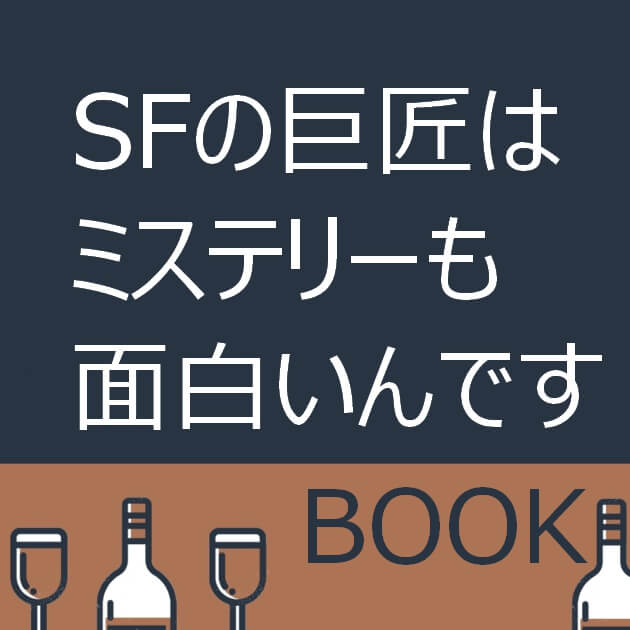作風
国内で短編小説、それもさらに短いショートショート作家といえば、星新一。
独創的なアイデアを短くまとめているからこそ、その作品群は読み手に強烈なインパクトを与えます。
先見の明を感じさせる作品も多く、現代社会の問題と重ねてあれこれ考えてしまうこともしばしばです。
「エヌ氏」などに代表されるように、星新一作品に登場するキャラクターはどこか記号的な存在で、昨今のキャラクター小説の対局をなす作風ともいえます。それでいて星新一節といいますか、台詞回しなどが特徴的で、個性がまったくないわけではないのも面白いところです。
ついでに申し上げますと、作品の評価とは関係ないですが、作者の名前もSF作家らしさがあって好きです(本名は漢字が違っていて星親一さんですが)。作風に合ったペンネームっていいですよね。
傑作ショートショート集『ボッコちゃん』
作者自選の代表的短編集に収録されている作品を一部ご紹介します。
『おーい でてこーい』
地上に現れた謎の巨大な穴。人々は、そこに廃棄物を捨て始め……。
その後を想像すると背筋が凍ります。
『殺し屋ですのよ』
それと悟られないように人の命を奪うことができるという女。その方法とは?
この女性、悪人には違いないのですが、頭が回るのは確かです。
『暑さ』
これから自分は罪を犯すかもしれないと男は警察官に語る。そう、こんな暑い日は……。
意味がわかると怖い話ですね。
『生活維持省』
人々の平穏無事な生活を守る「生活維持省」の役人の仕事、それは……。
最大多数の最大幸福をつきつめると、こういう社会になるのでしょうか。なんともいえないラストも秀逸。
『冬の蝶』『ゆきとどいた生活』
自動で機械が何でも行ってくれる時代の話。
便利さが一転して不便さにつながるという皮肉。普段どおりの一日をいつまでも迎えられるとは限らないのです。
『鏡』
ある夫婦が合わせ鏡で悪魔を呼び出すことに成功した。二人は、悪魔をいじめることでストレスを発散するようになるが、その行為はエスカレートしていき……。
身近な生々しさがある分、怖いと思える一篇です。
『肩の上の秘書』
肩に乗せた鳥型ロボットが、乱雑な言葉も丁重に翻訳してくれるというユーモラスな話。
本音と建て前を実体化すると、こんな感じなんですかね。
児童書・YA文学
子ども向けのシリーズとしては、講談社青い鳥文庫や角川つばさ文庫、理論社のYAセレクション(全10巻)などで傑作選が刊行されています。
子どもも読みやすい話が多いのが星新一作品のよいところです。最初に作品に触れたのが教科書だったという方も多いのではないでしょうか。
映像化作品
『世にも奇妙な物語』などでも何度か原作として取り上げられているようですが、DVDが発売されていて比較的視聴しやすいのは『星新一 ショートショート』でしょうか。過去にNHKで放映されたシリーズです。舞台劇風であったりアニメであったりと、作品ごとにさまざまな表現手法がとられており、制作者の演出の妙が魅力となっています。
また2022年、同じくNHKで『星新一の不思議な不思議な短編ドラマ』という実写ドラマが放送されました(全18話)。
おわりに
初めて星新一作品に触れるのであれば、やはり『ボッコちゃん』からがよいだろうと思い、紹介させていただきました。これを読めば、有名どころの作品はだいたい押さえられると思います。
余談ですが、私が「好きな作品」を一つ選ぶなら、それは『鍵』(『妄想銀行』収録)です。アイデアやセンスが「優れた作品」であればほかのものを挙げますが。「こういう人生もありかな……いや、人生ってこういうものじゃないかな」と思わせてくれるお話だと思います。
今回の記事で興味がわいた方も、ぜひお気に入りの作品を探してみてください。