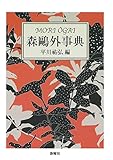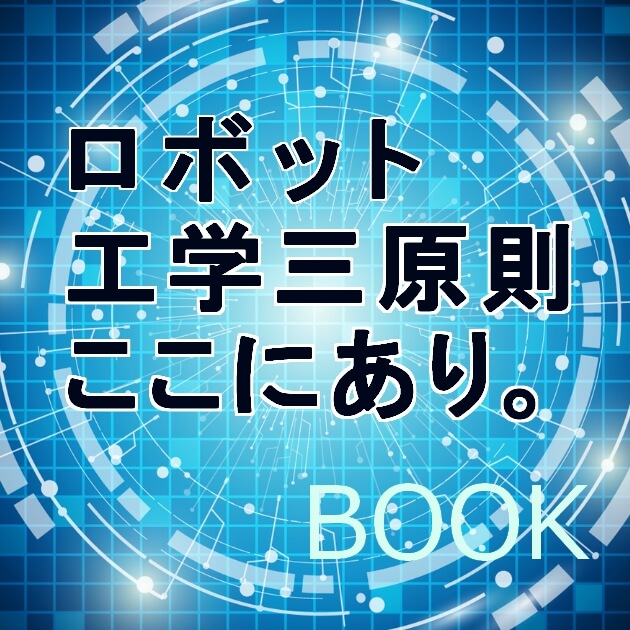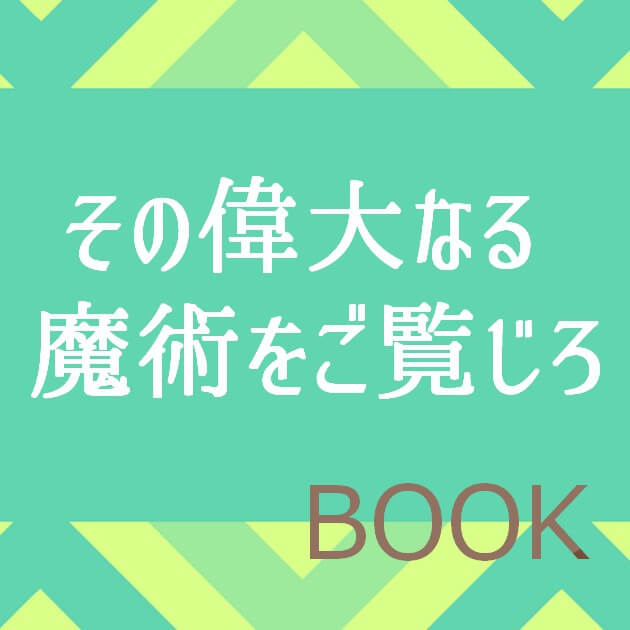はじめに
近現代文学史における著名作家とその作品を紹介するページです。(随時更新)
「文豪」の基準というものが明確にあるわけではないので、すべてこちらの匙加減ではありますが。
個別記事がある作品についてはリンクを張っていますので、興味をひかれた場合はそちらもご覧いただけますと幸いです。
なお、主な参考資料は『新訂総合国語便覧』(第一学習社)および『原色シグマ新国語便覧』(文英堂)です。
また、格式張らない、バラエティに富んだエピソードを知りたいという方には、『文豪どうかしてる逸話集』をおすすめしたいと思います。作者の進士素丸氏が、パフォーマンスチーム「en Design」さんのブログ(en通信)に寄稿した記事がきっかけとなり、出版に至った本だそうです。
森 鴎外(1862-1922)
代表作:『舞姫』『高瀬舟』『阿部一族』ほか
本名・森林太郎。石見国(現在の島根県)の典医の家の生まれ。初期は浪漫主義的作風でしたが、晩年は歴史小説・史伝を多く書きました。
夏目漱石とともに語られることが多い鴎外ですが、実は年齢でも作家歴でも漱石よりだいぶ先輩だったりします。
〈作品紹介〉
『高瀬舟』(1916)
弟殺しとして流罪になった男。しかし、その表情は妙に晴れやかで……。安楽死問題に切り込んだ短編小説。
〈関連サイト〉
- 森鴎外記念館(東京都文京区)
- 森鴎外記念館(島根県津和野町)
- 北九州市立文学館(福岡県北九州市):鴎外の書簡や書画を収蔵しています。
- 近代日本人の肖像[国立国会図書館]
- 森鴎外記念館(ベルリン):フンボルト大学の付属施設。国費留学した鴎外がベルリンで最初に下宿したという建物内にあります。
夏目 漱石(1867-1916)
代表作:『吾輩は猫である』『草枕』『こころ』ほか
初期のユーモアあふれる低回趣味の作風から、エゴイズムに主眼を置いた作風へと大きく変化していきました。
漱石を慕う若い作家は多く、毎週木曜日に交流会が開かれており(いわゆる「木曜会」)、その中には芥川龍之介や哲学者の和辻哲郎もいました。芥川に言わせると、漱石の発する「人格的なマグネティズム」に魅かれていたのだそうです。
〈作品紹介〉
『夢十夜』(1908)
「こんな夢を見た。」の書き出しで知られる連作短編。潜在意識下の不安感や恐怖心をえぐり出すサスペンス性と、独特の滑稽味をあわせ持った名作です。
〈関連サイト〉
- 漱石山房記念館(東京都新宿区)
- 夏目漱石デジタル文学館[神奈川近代文学館]
- 夏目漱石ライブラリ[東北大学附属図書館]
- 近代日本人の肖像[国立国会図書館]
幸田 露伴(1867-1947)
代表作:『風流仏』『五重塔』ほか
擬古典派の代表的作家。尾崎紅葉と同時期に活躍し、明治20年代には「紅露時代」と呼ばれる一時代を築きました。その男性的・理想主義的作風は、写実派の紅葉に対して理想派といわれます。
ペンネームの由来は「里遠し いざ露と寝ん 草まくら」。電信修技学校卒業後、電信技手として北海道に赴任していた露伴が、文学の道を志し、東京へ戻る道中に詠んだ句だそうです。
〈作品紹介〉
『観画談』
主人公は「大器晩成先生」というあだ名の苦学生。彼が奥州の古寺で遭遇した奇妙な出来事とは……?
〈関連サイト〉
- 博物館明治村/幸田露伴住宅「蝸牛庵」(愛知県犬山市)
尾崎 紅葉(1868※-1903)
※見出しの生年は太陽暦によるもの。書籍等によっては、1867年生まれと記している場合もあります。
代表作:『多情多恨』『金色夜叉』ほか
井原西鶴の影響のもと、擬古典主義・写実主義の作品を書きました。また、山田美妙の言文一致体(「です」体)に対し、雅俗折衷体(地の文は文語体、会話部分は口語体)を用いていましたが、のちに「である」体の言文一致体を完成させました。
「硯友社(けんゆうしゃ)」や「我楽多文庫(がらくたぶんこ)」の創設に携わったほか、泉鏡花をはじめとする多くの門下生を輩出したことでも知られます。親分肌の江戸っ子で、面倒見がよかったそうです。
〈関連サイト〉
- 近代日本人の肖像[国立国会図書館]
島崎 藤村(1872-1943)
代表作:『若菜集』『破戒』『夜明け前』ほか
北村透谷と雑誌「文学界」を創刊、浪漫詩人としてスタートを切るも、のち自然主義小説へ。旧家の出である父親の生き様に強い影響を受けた作品を書いています。
〈作品紹介〉
『三人の訪問者』(1919)
藤村が40代後半の時に発表した随筆。「冬」をはじめとする擬人化された三人の客が訪ねてきたことで、「私」の先入観が取り払われていきます。
〈関連サイト〉
泉 鏡花(1873-1939)
代表作:『高野聖』『婦系図』ほか
石川県金沢市出身。観念小説を書いた作家としても有名ですが、特筆すべきはその浪漫的・幻想的な作風です。
鏡花は尾崎紅葉を心底崇拝しており、「紅露」と並び称された幸田露伴に対しては敵意のようなものすら抱いていたとのこと。また、作品の中には紅葉をモデルにした登場人物(『婦系図』の真砂町の先生)もいるそうです。
〈作品紹介〉
『高野聖』(1900)
若かりし頃の旅僧が飛騨山中で出会ったのは、妖艶な美女で……。高野山の上人から「私」が聞いた怪異譚とは、いかようなものであったのか? 独特の語り口が印象的な、幽玄の世界を描いた物語です。
〈関連サイト〉
有島武郎(1878-1923)
代表作:『或る女』『生まれ出づる悩み』『カインの末裔』ほか
白樺派のひとり。内村鑑三らの影響もあってキリスト教に入信するも、その後懐疑的な立場に。
洋画家・小説家の有島生馬や小説家の里見弴は実弟です。
〈作品紹介〉
『生まれ出づる悩み』(1918)
家族のため生活のため漁師として働く「君」ではあるが、絵が描きたいという思いも……。実在の人物をモデルにした半自伝的小説。
〈関連サイト〉
- 有島記念館(北海道ニセコ町)
谷崎 潤一郎(1886-1965)
代表作:『細雪』『春琴抄』ほか
耽美的な傾向を持つ作風が特徴で、悪魔主義と呼ばれることもありました。
東京生まれですが、関東大震災後は関西に移住。日本の古典美に傾倒し、『源氏物語』の現代語訳を手がけたことでも知られています。
〈作品紹介〉
『陰翳礼讃』(1933)
日本建築等に見られる陰影の美しさ、日本人の美的感覚に主眼を置いた随筆。
〈関連サイト〉
- 芦屋市谷崎潤一郎記念館(兵庫県芦屋市)
萩原 朔太郎(1886-1942)
代表作:『月に吠える』『青猫』ほか
第一詩集『月に吠える』で、近代詩人としての地位を確固たるものにしました。「日本口語詩の真の完成者」とも評されています。
室生犀星とは、同じ雑誌(北原白秋編集の「朱欒(ザンボア)」)の同じ号に詩が掲載されたことが縁で生涯にわたる友人になりました。犀星曰く、朔太郎は「性格、趣味、生活、一つとして一致しないが、会へば談論風発して愉快」な友であるとのこと。
〈作品紹介〉
『猫町』 (1935)
萩原朔太郎が手掛けた数少ない小説。北越地方のK温泉を訪れた際、「私」は猫の精霊が暮らす奇怪な町に迷い込むことに……。
〈関連サイト〉
- 前橋文学館(群馬県前橋市):「朔太郎展示室」があり、原稿等を多数収蔵しています。
菊池 寛(1888-1948)
代表作:『父帰る』『恩讐の彼方に』『真珠婦人』ほか
テーマ小説を多数書いたことで知られる、通称「文壇の大御所」。芥川賞・直木賞の創設者、雑誌『文藝春秋』の創刊者です。モットーは「生活第一、芸術第二」。
また、同じく新思潮派の芥川龍之介や久米正雄とは一高の同級生でもあります。
〈作品紹介〉
『無名作家の日記』(1918)
主人公は作者自身、その同級生は芥川や久米をモデルとしているのではないかといわれ、話題になった作品。京都の大学に通う小説家志望の「俺」は、東京にいる同級生らを過剰なまでに意識しつつ、鬱屈とした日々を送っているのですが……。
〈関連サイト〉
- 菊池寛記念館(香川県高松市)
夢野 久作(1889-1936)
代表作:『ドグラ・マグラ』『押絵の奇蹟』ほか
ペンネームの由来は、故郷・福岡の方言で夢想家を意味する「夢の久作」です。怪奇幻想趣味が色濃く出た作風が特徴。
本名は杉山泰道で、実父は政界の黒幕といわれ、明治~昭和期に活躍した杉山茂丸。また、長男はインドで緑化事業を行い、「緑の父(Green Father)」と呼ばれた杉山龍丸です。杉山三代、生き様は三者三様ですが、いずれも歴史に残る活動をしています。
〈作品紹介〉
『瓶詰地獄』(1928)
三本の瓶の中から発見された手紙には、無人島で起こった悲劇が記されており……。いくつもの解釈が考えられる作品です。推理小説家による考察では、北村薫著『ミステリは万華鏡』所収のものが有名でしょうか。
『ドグラ・マグラ』(1935)
精神病科で目を覚ました記憶喪失の「私」と、二つの事件の容疑者「呉一郎」の関係とは……。その特異な作風から、『黒死館殺人事件』『虚無への供物』と並んで日本探偵小説三大奇書に数えられています。
『何んでも無い』(1936)
『少女地獄』の中の一篇。虚言癖を持つ看護婦「姫草ユリ子」が破滅に向かうさまを、彼女の雇い主である医師の視点から描いた作品です。
内田 百閒(1889-1971)
代表作:『冥土』『阿房列車』『百鬼園随筆』ほか
夏目漱石の門下の一人。ユーモアや俳味に富んだ随筆で知られています。
法政大学でドイツ語を指導していた百閒。教師時代の教え子らが開いてくれていた誕生パーティー「摩阿陀会(まあだかい)」にまつわるエピソードは、黒澤明監督の『まあだだよ』のモデルとなっています。
〈作品紹介〉
『東京日記』(1938)
牛の胴体よりもっと大きな鰻(うなぎ)が、ぬるぬると電車線路を数寄屋橋の方へ伝い出した……。東京を舞台に繰り広げられる23の奇妙な物語。
『サラサーテの盤』(1948)
夫のレコードを返してほしい、そう話す亡き友人の妻。彼女は「私」が友人から借りた物を事細かく把握しており、「私」は不思議に思うのですが……。映画『ツィゴイネルワイゼン』の原作です。
〈関連サイト〉
芥川 龍之介(1892-1927)
代表作:『羅生門』『薮の中』『河童』ほか
子ども時代からその秀才ぶりを発揮していました。夏目漱石の激賞を受け、デビュー時から注目を集めます。
〈作品紹介〉
『黄粱夢』(1917)
中国の古典小説『枕中記』を題材にした掌編ですが、結末が原典とは正反対になっています。不思議な枕を使い、夢の中で一生を送った主人公が目を覚ますと……。
『枯野抄』(1918)
松尾芭蕉の臨終に際し、さまざまな思いを巡らせる門人たちの姿を描いた作品。人間のエゴイズムを克明に描写しており、恩師・夏目漱石の死が投影されているともいわれます。なお、漱石の葬儀の様子については、『葬儀記』(青空文庫)などに描写が見られます。
〈関連サイト〉