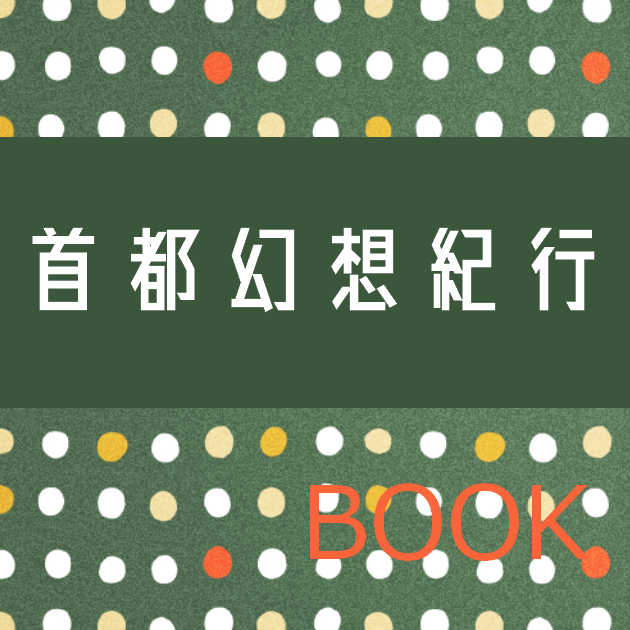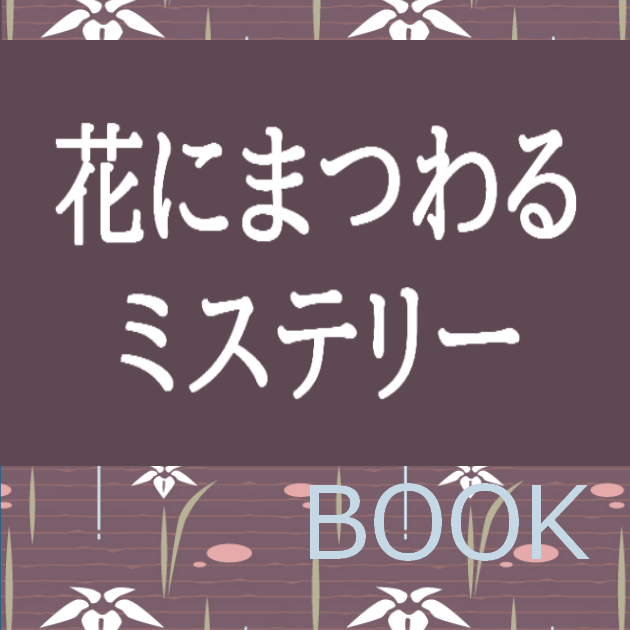僕と彼女
ヤン
頭でっかちでアンバランスな体形をした主人公。いかにも人外といった見た目ですが、真横からだと胎児のようにも見えますね。
オープニングでは、ヤンと呼ばれる人物が謎の装置〈ガラージュ〉に座らされていました。このため、「この世界は仮想現実(VR)で、主人公はヤンのアバターのようなもの」という解釈をしていたのですが、内実はことのほか複雑です。
プレイを進める中で、記憶喪失になり変身したヤン=主人公というところまでは当たりを付けられたものの、主人公とシェンの2人に分裂していたというのはさすがに予想外。
要はジキルとハイドのような解離……? いや、単純に善悪に分かれたわけでもないので、やっぱり違いますかね。
(追記)久しぶりにスティーヴンスンの小説を読み返してみたところ、ジキルとハイドもそう単純な話ではなかったことに気づかされました。
シェン
自分はつなぎに過ぎないと語るシェンから託されたバトン。主人公こそがアンカーであり、待ち受けるのは「終わり」のみ。
自ら消える覚悟を決めるまでのシェンの心中を思うと、何とも言えません。その分、福寿荘のちよさんの「シェンはヤンだった でもシェンがシェンであったことも確かなんだよ」という言葉にはしんみりしました。
それは本当にそうだと思います。断片的に垣間見える分裂前のヤンの言動はひどいものばかりでしたが、シェンに関しては理性的で親切なイメージが強かったです。
名前のない主人公
シェンと同様に、主人公もヤンであってヤンではない。
研究者のガタリは「君は名づけられる前の存在のように思えるのだ」と言いました。やはり主人公には赤ん坊のようなイメージがあるのでしょう(クリア後に知ったのですが、公式関係者がつけた主人公の愛称は「バブちゃん」なんだとか)。
胎児に似た主人公が最終的に水門から出ていくさまは、出産の過程を描いているようでもあります。オープニング等の情報がなければ、私は主人公=外のヤンとルウの子どもだと思っていたかもしれません。夢野久作の『ドグラ・マグラ』の解釈のひとつ、胎児が見た夢説みたいな感じですね。
外のヤン
「僕は彼女を殺した」──衝撃の一文から始まる〈そとのヤンの手記〉。そこからは、「僕(ヤン)」と出会う前に酷い環境に置かれていた「彼女(ルウ)」が、「僕」に対しても暴力・被暴力の関係しか築けなかったことが読み取れます。
一方通行のコミュニケーション。一方通行の道とその道を決まった方向にしか走行できない車両。
まるでガラージュ世界の移動方法ですね。最初は暴力をふるう気などなかった「僕」ですが、だんだん罪悪感と快楽の区別もつかなくなり、無感覚になっていった、と述懐します。
白状すると、私はこの手記を読んだとき、『ガラージュ』の物語が現実の男女の問題に帰着することに少しがっかりしました。〈なんでもない石〉が〈再生石〉に変わった後、ちよさんが「意味のなかったものが意味を持つ」ことで「また世界が狭くなっちまった」気がする、と話していた気持ちがわかるというか……。
それはさておき、一人称は機械のヤンが「俺」、シェンが「私」、主人公が「僕」(具体的な台詞はないものの、アイテム名が〈僕の楽譜〉であることから)なので、主人公が外のヤンの人格に一番近いのかもしれませんね。
外のルウ
お面を被った顔のない人たちに囲まれて育った外のルウ。彼らは、彼女に向かってたくさんのゴミ(暴言や暴力)を捨てました。
作中ではかなり比喩的な表現で境遇が語られていますが、外のルウは家庭や学校で虐待を受けたり、いじめられたりなどしていたのでしょう(周囲にいる人間の多さからすると、一般家庭ではなく、どこかの施設で育った可能性もあると思います)。
終盤のルウの話によると、彼女はヤンに対して「触れて/触れないで」「ぶって/ぶたないで」等、あらゆる矛盾する願いを持ち、二人はまるで殺し合っているかのようだった、といいます。Mr.Childrenの「掌」の歌詞をさらに壮絶にした感じかもしれません。
カゲ
プシケ
〈カゲ〉の一人であるプシケ。初めて会ったときは、人間の姿に近いことに驚きました(白瓦斯屋の雌機械たちと似ても似つかないポスターは、広告詐欺だと思っていました)。
プシケ(プシュケー)には古代ギリシア語で「魂」「心」といった意味があります。
ユング心理学的には、「合理的であるとともに非合理的であり、意識的であるとともに無意識的であり、個人的であるとともに集合的である生命活動全体のこと」らしいです(【参考】『心理学辞典』有斐閣、1999年)。被験者の深層意識から生み出されたガラージュの世界を象徴するようなネーミングではありませんか。
また、実験工房で手に入れた〈シャドーに関する考察〉では、カゲではなくシャドーという呼称が使われていました。英語で呼ばれていると、こちらもユング心理学のシャドウ(簡単に言えば心の暗部のこと)を連想してしまいます。
主人公のカゲ
こちらの外見は、これまで出会ったどの女性のカゲともかけ離れており、またびっくり。
強いて言えば、古い絵巻物に登場する餓鬼(飢えと渇きに苦しむ餓鬼道に落ちた亡者)に似た容貌というか。もっとも彼が求めていたのは食べ物ではなく、元の世界へとつながるアイテム、〈原想体〉=運動靴と〈刻印石〉でしたが。
カゲはこの世界において異質な存在、言い換えれば本来の世界との結びつきが強い。この世界にこだわるヤン(分裂前のヤン)はカゲに嫌悪感・敵意を持ってカゲ狩りをし、いい加減にこの世界を終わらせたいヤン(シェン・主人公)はカゲとの再会を目指したわけですね。ヤンの中には相反する2つの感情が渦巻いていたのでしょう。
閉ざされた世界で自分とは独立して「影」が存在している点などは、村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』のようでもあります。
楽譜とオルゴール
〈僕の楽譜〉と〈ルウの大切なもの〉は、外のヤンとルウの思い出の曲であったことが終盤に明らかになります。
しかし玩具店のブルカニロさんは、昔はみんな楽譜とオルゴールを持っていたのに、今では誰もきちんと歌に耳を傾けようとしなくなった、と言います。ひょっとすると、外のヤンの心が殺伐としていて音楽への関心が薄くなっていたのかもしれませんね。あるいは、思い出の曲を聴くのはつらいから遠ざけておきたい、という気持ちの反映でしょうか。
ブルカニロさんは「雛形」、また走行装置製作所のエヌサンは「まがいもの」という表現を使っていましたが、住人の中には自分たちが何かを模したものに過ぎないのではないか、という疑念を持っている者がいるようです。
ちなみに、ブルカニロという名前の由来は、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』であると思われます。『銀河鉄道の夜』のブルカニロ博士は、第三次稿までは登場シーンがあったものの、その後存在が抹消されてしまったという意味深なキャラクターです。
生態系と釣り
母なる汚水
ガラージュの世界では「全てのものは汚水から生まれた」といいます。汚水こそがこの世界における母なる海ということでしょうか。
機械のヤンはジュースを恐れ、また雌狩りを行いましたが、これは外のルウに対する罪悪感等の裏返しであったのだと思います。ただ、ヤンが執着していたこの世界を維持するには、結局のところ燃料も汚水も雌機械に依存せざるを得ないあたり、皮肉めいたものを感じますが。
燃料と汚水の増産のために改造されたジュースはもはや異形と化していましたが、その姿にはエフェソスのアルテミス像のような神々しさもないではありませんでした。
釣り、ワンスイとキョム
釣りと言えば一般的には魚釣りをまず思い浮かべるところですが、本作では蛙やカニが対象である点がやや謎です。〈ヤンの夢日記〉の内容からすると、外のヤンは蛙(と運動靴)に何かしら思い出があるようではありますが……。
童話や昔話に登場する蛙やカニについては、臨床心理学者の河合隼雄氏の著作の中に、興味深い記述があったので紹介しておきます。
蛙も蟹も共通な特性は、両者とも水陸両方に住めることである。水と陸との間を往来するもののイメージは、意識と無意識をつなぐもの、あるいは、無意識より意識界へと出現してくるものを思わせる。
(河合隼雄『昔話の深層 ユング心理学とグリム童話』講談社+α文庫)
この説を踏まえると、しゃべる大蛙ワンスイとキョムが現実世界と関わりのあるアイテムを主人公にくれたり、この世界の時を止める力を持っていたりするなど、高次元ないし境界線上の存在なのではないかと感じさせる節があるのにも納得がいきます。
消えゆく機械たち
終わりの終わり
時が動き出してからの章名は「終わりの終わり」。「終わりの始まり」とかじゃないんですね。とっくの昔に終わりには向かっていたということでしょう。
ヤンのカゲ、シェン、ジュースと重要キャラクターと出会う過程で、他の機械たちの様子もおかしくなっていき、工場スタッフ3人は姿を消しました。
そして、権兵衛さんや治郎兵衛さんには煙たがられ、隣人のハジメさんにまで「怖い機械」だと言われてしまいます。主人公がいずれこの世界を消し去る存在であることを考えれば、意識的かどうかはさておき、彼らなりの精一杯の抵抗であったのかもしれません。
ビスとルウ
〈ルウの日記〉には「ビスは私を哀れんでいる」「私をそのままに見てくれる機械なんて居ない」など、コンプレックスと孤独を抱える彼女の心情が綴られていて、読んでいると胸が痛くなります。
ただ、その後のルウとビスさんの言動を見ていると、そこあるのは決して哀れみだけではなかったと思いたいところです。
本田とエヌサン
台車百式まで改造を終えると、燃え尽き症候群のようになってしまった本田さんがこんな話をします。自分はエヌサンに何もしてこなかったけれど、それがこの世界の雄機械にとっては普通のことで「ほんとうにつまらない当たり前だ」と。
正直「この世界の夫婦観、男女の関係性って古いな」とは思っていました。外のヤンの両親がそんな感じだったのでしょうか。あるいは、作中の時代設定がゲームの発売された1999年よりも古いのかもしれません。
また、ひとつ気になったのが、ガラージュの世界では「夫婦」という呼び方や「子ども」という概念が存在しないと思われる点です。これは、外のヤンとルウが恋人関係であってまだ夫婦ではないということに起因するのではないかと考えたのですが、どうでしょう。
ニューム、宮、ツル
宮工務店の従業員ニュームが突然消えてしまったのは、かなりショックでした。ゲーム前半は「彼は新しい機械ゆえにメンタルが強いのだろう」と思い込んでいたのですが、実のところ一人でいろいろと葛藤していたのです。
残された〈ニュームの日記〉からは、最初のうちはツルさん・宮さんに可愛がられて働く初々しい姿が読み取れますが、徐々に内容が暗くなっていきます。
閉じた世界から出よう、自分で道を作ろう、そう決意して行動していたニューム。高いところ、そして遠くへ行きたいと夢を語っていたニューム。しかし最後の台詞は「僕が欲しかったものはあそこには無かったよ…」「地面が消えちゃったんだ…」。希望と絶望の落差が浮き彫りになって気分が沈みます。
ただ不思議なことに、長らく意識のはっきりしていなかった宮さんが目を覚まし、それが主人公のおかげのような気がする、とツルさんに言ってもらえたのは数少ない救いでした。復活した宮さんは、江戸っ子のような親分肌の性格が気に入っています。
リーとリズ
白瓦斯屋2号店の抽斗の中で見つかった〈なんでもない石〉。
どうしてリズはこんな俺を嫌いにならないのだろう、どうしてただの石ころを嬉しそうに渡してくるんだろう──そこにはいっしょに〈リーの殴り書き〉が封じられていました。
あんたは普通じゃないだの、イライラするだの、自発的に何かを知りたがるのは「わざわざ問題を増やしに行くようなもん」だの、思えばリーさんには序盤から散々な言われようでした。
しかし本人も語っていたように、彼にとってはリズさんとの今の生活がすべてで、それを失いたくなかったのでしょうね……。ニコニコしながら石を見せるリズさんの様子を想像すると、切なくなります。
ジュースによる人物評
「壊れた世界の先の世界」でジュースはさまざまな話をしてくれます。その内容は非常に興味深く、私が知ることのできた範囲では次のような感じでした。
- ツル:自分の気持ちに正直でかわいい。「わたしもあんな風になりたかったけど ずいぶんひねくれちゃった…」
- ギムノン:「色々気がついているけど 真面目だからあんな風にしかなれないの」
- プシケ:この世界のことは何でも知っている反面、自分のことは何も知らない。「プシケはあなたが見たわたしだからよ」
- メディチ:ヤンの妄想であり嫉妬。「あなたはとても嫉妬深かった」
- 治郎兵衛:いつも哀れ。「自分で選んだことしか選べない 自分の望んだことしか見えない」
- ルクー:「この世界で眠ることの出来る機械はルクーだけ」
- ガタリ:よくわからない。容子がいなくなって寂しいのだろう。「アインがあんなことしなければ 容子だってあんな風にならずに済んだのに…」
- アイン:「自分でも残酷だって知っているくせに残酷でいられる」
- ラオ:頑固者。「自分の思いつきで頭がいっぱい」
ツルさんが素直でかわいい、という点については私も同意見。宮さんが目を覚まして嬉しそうにしている姿を見たときは、こちらまで嬉しくなってしまいました。あとに続くジュースの台詞には切なくなりますが。
メディチは外のヤンの暴力性や支配欲の現れかと思っていたのですが、嫉妬心の反映でしたか。
ガタリが他の住人と離れて〈番屋〉で暮らしているのは、アインとの確執が原因なのでしょうか。他の雌機械と外見が違う、しかも一切しゃべらない謎の存在、容子さん。彼女の身にいったい何が起きたのか……。
個人的に一番意外だったのはギムノン。ハジメさんほか、冷たい態度に変わってしまうキャラクターがいる中で、物語後半はギムノンにずいぶん癒されたものです。周りがそわそわしているのに対し、ギムノンはヌシの話で盛り上がったりしていたので、「のん気だなあ」なんて考えていたのですが、彼の一面しか見えていなかったのかもしれませんね。
ガラージュとは
ガタリとアイン
ガタリとアインは、現実世界のお医者さんに相当するらしいですね。ガタリの名前は、精神分析家・哲学者のフェリックス・ガタリに由来するのでしょうか。
ガタリとジル・ドゥルーズの共著『アンチ・オイディプス』の目次だけちらっと見ても、「分裂者の散歩」「欲望機械」「器官なき身体」「劇場か工場か」など、ガラージュ的に気になるフレーズが登場します。
アインは、ヤンの願望を実現するために自分は奉仕してきたのだと話します。「その望みの実現こそがこの世界の意味」だから、と。
「その選択がどのように愚かであろうと どのように残酷であろうと どのように無意味であろうと」「私はその結果を見届けなければならない」
「この世界は終わらせることでしか救われない世界なのだ」
ヤンのヤンによるヤンのための世界ですね。
君の世界
ここは「ヤンの世界」であるとガタリは断言しましたが、話はそう簡単ではありません。
「しかし世界というものは それがどんなに限定された世界であれ 記憶された過去が羅列されるだけの単純なものではありえないのだ」
「我々は我々が自覚するより 遙かに多くの情報を受け取りながら生きている」
写真や動画を撮ったり、録音したりした内容を後で確認すると、撮影時には気づかなかったものが映っていたり、動物の鳴き声や乗り物の音が入っていたりして「あれっ?」と思うことがありますが、そういうイメージですかね。
この世界は「過去の集積」であると同時に「可変的な有機体」であり、それゆえにガタリや主人公も自由に思考したり行動したりできるのだ、とガタリは言います。
この世界の住人は、雄機械は外のヤン、雌機械は外のルウをベースとしつつ、さらには外のヤンの知人等の人物像を投影した存在であり、ガラージュが起動して以降はそれぞれが自我を確立していった……そんな印象を私は抱きました。
リズさんに対して複雑な心境に置かれているリーさん、愛しいジュースを傷つけることなどできないと語るコッペル、ルウを優しく気遣うビスさんなど、それぞれに外のヤンの持つ多面性が表れているのではないかと思います。
臆病な道代さんを「いじめたくなる」というウリブールの発言や、「私以上にジュースを理解している機械は居ない」というコッペルの発言には歪んだ感情が見え隠れしますし、権兵衛さんの雌機械に対する変態じみたコメントも外のヤンの一部かもしれない、と考え出すと微妙な気分になってきますが……。
記憶というもの
ジュースと初対面を果たしてから灯台2階へ引き返すと、過去が終わった、居場所がなくなった、あなたに殺される、とレイコ・道代・シャンのカゲにののしられます。いつまでも過去にすがっているわけにはいかないように思いますが、過去の存在らしい彼女たちにしてみれば、死活問題なんでしょうね。
その後、アインは記憶の操作についての話をします。それは実は難しいことではなく、記憶の封印・改ざん・交換といったことは誰もが全部無自覚にやっている、と。
「記憶などというものは、所詮、望まれたものに過ぎない」
プシケは、自分は「望まれただけの存在」であり、望む者がいなければ消えてしまう、自分の役目は終わった、と言っていなくなりましたが、その台詞を思い出しました。
振り返ってみると、三人娘のカゲやジュースを除けば、主人公に対して当たりが強い女性というのはいませんでした。序盤からおばあちゃんの知恵袋といった感じで頼もしいちよさんをはじめ、全体的に雌機械の方が達観している印象を受けましたし。
これは外のルウに許されたい、という外のヤンの願望なのか。そう考えたのですが、終盤のルウの言葉で少し認識が変わります。
「ジュースもプシケもヤンが望んだ言葉を喋った… あなたがこの世界できいたのは… ヤンが望んだ言葉…」
プシケだけでなくジュースも、そして他の住人すべての言葉がヤンの望んだものだったというのです。だとすると、自罰的なものも感じますね。
庭
ジュースは、ここは「出来の悪い不細工な庭」だけれど「あなたの中なんだから嫌いになれない」と言いました。
App Store等のゲーム紹介では、〈ガラージュ〉は被験者の深層意識に働きかける精神治療装置であると説明されていますが、このジュースの「庭」という表現から私は箱庭療法を連想しました。VR版箱庭療法ですね。
「問題なのは何が正しいかって事じゃなくて 何をすべきかって事なんじゃないのかい?」
「鎖を断ち切るんだよ 繋りの環の外に出なくちゃいけないだ」
「あんたは今死んでいるようなものなんだ あんたの時間がほんの少し巻き戻っているだけなんだ」
「あんたが此処でなにをしようと そんなことはあんたが自分自身に対して望んだことなんだよ 此処には他人はいないんだ」
ただ、ニュームがどこにも行けなかったように、ここは閉じた世界です。自問自答、一人で過去に向き合い、気持ちを整理することは無論必要でしょうが、ちよさんの言う通り「他人はいない」以上、広がりはありません。
エヌサンは「水門の向こう側にはどこまでも続く深淵が広がっているんだって」と話していました。その先は他者がいる世界、現実でしょう。
「終わろう」
鳥は卵の中からぬけ出ようと戦う。卵は世界だ。生まれようと欲するものは、一つの世界を破壊しなければならない。
(ヘルマン・ヘッセ著、高橋健二訳『デミアン』新潮文庫より)
プシケは「答えは一つではありません 答えが終わりであるならば」と話していました。これは、「終わり」以外に道はないけれど、どう終わるかが重要だと言いたかったのかもしれませんね。
上では『デミアン』の一節を引用しましたが、終わりは時にひとつの始まりです。水門を開けるまでずいぶん遠回りをしましたが、それも主人公にとっては必要なことだったのでしょう。
garageは「ガレージ、車庫」「修理工場」等を意味する単語ですが、語源としては「保護する所、避難所」というニュアンスになります。
どうして〈ガラージュ〉だったのか、「望むもの」は得られたのか。想像を膨らませていくと、面白いですね。