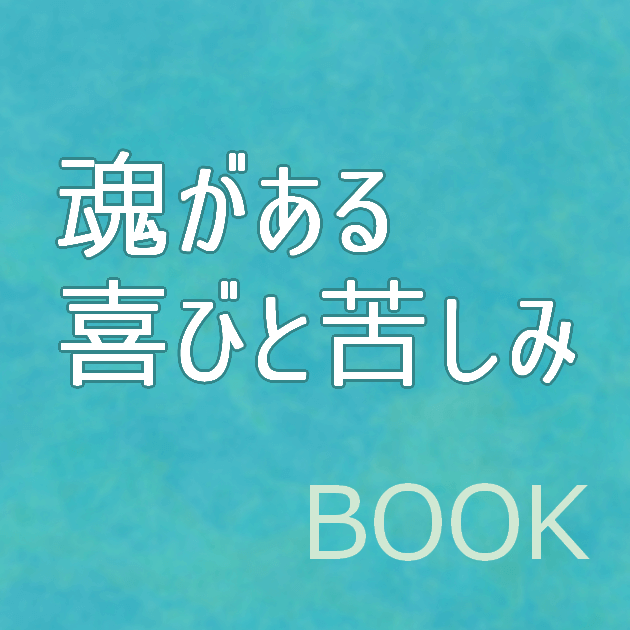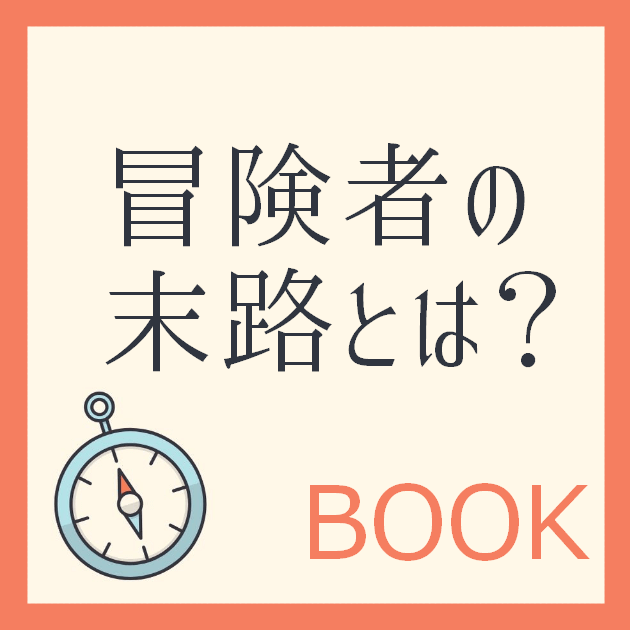今回は、ドイツ後期ロマン派の作家フーケーの小説『水妖記(ウンディーネ)』(原題:UNDINE)をご紹介します。ジャン・ジロドゥの戯曲『オンディーヌ』の原作としても有名な、水の精を主人公とした悲しい愛の物語です。
なお、本記事では岩波文庫の柴田治三郎訳を参考にしています。
あらすじ
騎士フルトブラントは、化け物が出るという噂のある森を通り抜け、美しい湖の岬に立つ漁師小屋にたどり着いた。
そこで出会ったのは、年老いた漁師の夫婦と養女ウンディーネ。やがてフルトブラントはウンディーネと恋仲になるが、この不思議な美少女の正体は、魂を持たない水の精であった。
水の精の伝説
物語のパターンとしては、羽衣伝説などのような異類婚姻譚にあたりますね。
ドイツ語の「ウンディーネ(Undine)」(フランス語では「オンディーヌ(Ondhine)」、英語では「アンダイン(Undine)」)という名称は、スイスの医学者・錬金術師パラケルススの造語「ウンディーナ(undina)」に由来するとのこと。
また、水の精は人間の男性と結婚することで永遠の魂を得る、といった本作の内容も、パラケルススの記述やドイツのニンフ伝説を参考にしているようです。
ちなみに、アンデルセン作『人魚姫』でも似たような設定が登場しますが、これは『水妖記』に影響されている面があるのだとか。
内容紹介と感想
恋人たちが出会った経緯
本作が発表されたのが1811年。さらにその何百年も昔の話として語られていますから、森が「異界」として恐れられ、人々が自然と深く関わりながら生きていた時代の出来事でしょうか。
15年前、湖に消えた実子と入れ替わるように漁師の前に現れたのが幼いウンディーネでした。妖精にまつわるヨーロッパの伝承、「取り替え子(changeling)」を想起しますね。
人間とは違い、魂のない水の精たちは、死ぬと無に帰してしまいます。強欲な水界の王は、一人娘のウンディーネに魂を得させるべく、彼女を人間界に送り込んだのです。
実は、騎士フルトブラントの来訪にも、ウンディーネの伯父キューレボルンが関与していました。このタイミングで大水が出たのは、騎士がすぐに旅立てないように、川を縄張りとするキューレボルンが力を発揮していたからだったのです。
魂がないということ
結婚前のウンディーネは、わがままで気まぐれ、いたずら好きで、18歳近いというのに非常に手が焼ける女の子でした。
彼女の良く言えば天衣無縫、悪く言えば傍若無人な姿を見て、漁師のおじいさんは「月の世界からでも降って来た子だろう」と考えたことさえありました。『竹取物語』のかぐや姫を思わせるようなたとえですが、西洋文化的にはルナティックというニュアンスなのかもしれません。
『竹取物語』の月の住人が悩みや苦しみとは無縁らしいところなどは、『水妖記』の水の精に通じるものがあると思いますが、方向性はまるで真逆。月の住人が涅槃の世界の存在であるのに対し、水の精は非常に子どもっぽいのです。
本作で魂がないということは、感情がないということではなく、他人に対する配慮や人情の機微を理解する力が欠けているということを意味しているのではないでしょうか。
ウンディーネは豹変す
「魂って重い荷物に違いないわ。とても重いものに違いないわ。だって、そのかたちが近づいて来るだけでも、もう私には居ても立ってもいられないような心配や悲しみが影のように覆いかぶさって来るんですもの。いつもはあんなに軽い、楽しい気持でいられたのに。」
こんなことを言っていたウンディーネですが、結婚後はそれまでとは打って変わって、慎み深い落ち着いた女性に急成長。魂を得たウンディーネは、恩人である漁師のおじいさん・おばあさんに対して感謝の念を抱くことができるようになったのです。
彼女は愛する夫にすべての事情を告白しました。ウンディーネは相手への思いやりから、自分のことを恐いと思うなら今ここで棄ててくれてもかまわない、と伝えます。
それでも妻を絶対に見捨てないと誓うフルトブラント。
このまま終わっていれば美談だったのですが、残念ながらそうはいきません。
もう一人の娘
ここで、数奇な運命にもてあそばれた人物がもう一人登場します。フルトブラントに好意を寄せている気位の高い美女ベルタルダです。
領主の養女である彼女は、騎士が森に向かうきっかけを作りました。しかも驚くべきことに、彼女こそがキューレボルンがさらった老漁師の本当の娘だったのです。
その事実を知ったウンディーネは、サプライズとしておじいさん・おばあさんを呼び寄せ、ベルタルダに引き合わせようとします。
ところが、ベルタルダは生みの親を偽者扱いし、「金で買われた貧乏人」だとののしりました。友人に喜んでもらえるものと期待していたウンディーネは激しいショックを受け、「あなたには魂があるの?」と思わず叫んでしまうのでした。
本作において「魂」の在り方が問われている象徴的な場面のひとつです。
城での生活
養女の心無い仕打ちには領主たちも幻滅。結果、ベルタルダは彼らに縁を切られ、路頭に迷うことに。さすがに、これはかわいそうですね。ウンディーネたちも彼女を不憫に思い、騎士の住まいである城に友人を迎え入れます。
皮肉なことに、この親切心が新たな悲劇を生みました。夫がベルタルダに心移りしてしまったのです。フルトブラントはベルタルダをひいきし、彼女は我が物顔に振る舞うようになりました。
事前にわかっていた属性(年齢や出身地、趣味など)の違いについて、後から不満が出てくる、というのは現実でもままありますが、種族を越えた結婚をしたフルトブラントも、人間同士で結婚していたら…と後悔し始めたのです。
結婚に至る経緯や、キューレボルンたち水の精がちょっかいを出してくることを考えれば、フルトブラントに対する同情心が私にもないわけではありません。
しかし、現在のウンディーネは、かつてのような身勝手な少女ではなく、思慮深く心優しい女性ですので、どうしても彼女の方を応援したくなってしまいます。この点、城の召使がウンディーネを慕っていることや、漁師のおじいさんが一貫してウンディーネの味方であることは、救いに感じました。
破局
ウンディーネは夫や友人に変わらぬ愛情をそそいでいますが、先述の通り、水の精には微妙な感情、複雑な人間性は理解できません。
キューレボルンたちはウンディーネがいじめられていると早合点しては、フルトブラントやベルタルダに嫌がらせをしてきます。ウンディーネの言うように「愛の喜びと愛の悲しみは、たがいによく似た優しい姿の、親しい姉妹の仲」であることなど、水の精は想像だにしないのです。
その後も波乱の展開が続き、フルトブラントはしつこい水の精たちに怒り心頭、ついには妻の誠意まで疑い出します。結局、ウンディーネは涙ながらにドーナウ川に身を投げるのでした。
二度目の婚礼と葬儀
配偶者がタブーを犯してバッドエンド、という流れは異類婚姻譚でよく見られますが、本作も同様の結末を迎えます。
フルトブラントが再婚(厳密には死別ではないので重婚?)すると、ウンディーネは、本人が望むと望まざるとにかかわらず、彼の命を奪いにいかなければなりません。
このため、水の精の出入り口となる泉を予め封鎖したり、その後も夢の中で警告を発したりするなど、ウンディーネは夫たちを守るための行動をとってきました。
しかし、その苦労はあっさりと水泡に帰すことになりました。まあ、目次に「婚礼」と「葬儀」の文字が並んでいる時点で、フルトブラントの運命は読む前からわかりきっていたわけですが……。
それにしても、ウンディーネは最後の最後までいじらしかったですね。魂がないままであれば、こんな悲しみや苦しみを味わうこともなかったはずなのに。
けれど、仮に魂を手放す方法があったとしても、ウンディーネはそんなことはしなかったに違いありません。なぜなら、魂があるからこそ得られた喜びや幸せもあるのですから。
本作では男女関係の描写に重きが置かれていましたが、恋愛にかかわらず、幸福と不幸は表裏一体。それが人生、魂を持って生きるということなのだと思います。
おわりに
冒頭でも触れた戯曲『オンディーヌ』をはじめ、『水妖記』からは多くの派生作品が生まれています。そういった後世の作品の原点を知る、という観点から本作を読んでみるのも面白いのではないでしょうか。
なお、比較的新しい日本語訳としては光文社古典新訳文庫の『水の精(ウンディーネ)』(2016年に刊行)があり、現在は岩波文庫の『水妖記』等よりそちらの方が入手しやすいかもしれません。