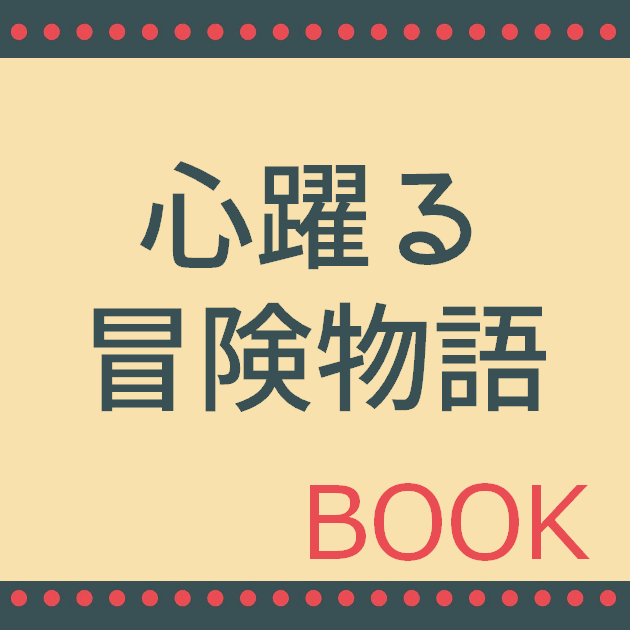1886年に発表された中篇小説『ジーキル博士とハイド氏』(原題:Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde)は、『宝島』と並ぶスティーヴンスンの代表作です。
※本記事では岩波文庫の海保眞夫訳を参考にしています。
あらすじ
舞台は19世紀、ヴィクトリア朝ロンドン。弁護士のアタスン氏にはある悩みの種があった。それは、ジーキル博士から保管を頼まれた遺言状についてである。
そこには、博士が亡くなったり行方不明になったりした場合、「友人で恩人」のハイド氏に財産を相続させるように、と記されてあった。
聞くところによると、正体不明の男ハイドは、幼い少女に怪我を負わせても何とも思わないような非情な人物であるらしい。紳士ジーキルと極悪人のハイド、本来ならば接点があるとは到底思えない2人の関係とはいったい……?
主な登場人物
ヘンリー・ジーキル
50代の学者。医学博士・法学博士等の肩書を持つ名士で、博愛家として知られる。
エドワード・ハイド
ジーキル宅に出入りしている謎の小男。見る者に不快感を与える邪悪な青年。
ゲイブリエル・ジョン・アタスン
弁護士。感情をあまり表に出さない。自分に厳しく、他人には寛大な性格。
ヘイスティ・ラニョン
医師。ジーキルやアタスンとは旧知の仲だが、近年ジーキルとは疎遠になっていた。
内容紹介と感想
事の経緯
素性の知れない悪党
神出鬼没の小男ハイド。そのHydeという名にはhide(隠れる)という意味もかかっているようです。
アタスンの友人は、ジーキルが若い時分の無軌道な振る舞いをネタにゆすられているのではないか、と推測します。確かに、それはありそうな話ですね。
そこでアタスンは、力になれることはないかとジーキルに申し出ました。しかし、ジーキルは感謝するどころか、プライベートな問題なので口出し無用、と突っぱねます。なぜそこまで強く反発するのか、引っかかるところです。
カルー殺害事件
1年後、大事件が起きます。国会議員のサー・ダンヴァーズ・カルーがハイドに撲殺されたのです。ハイドは全国に指名手配されますが、その後ぱったりと姿を消しました。
ハイドとは縁を切ったと話すジーキルは、再びラニョンらと友達付き合いをするようになり、慈善活動にも精を出します。
こうしてしばらくは平穏な日々が続いたのですが、ジーキルは何かの病気にかかったらしく、書斎に引きこもるようになってしまいます。
ジーキルとハイドの筆跡の類似。旧交を温めていたはずが、一転してジーキルに対し嫌悪感をあらわにするようになったラニョン。アタスン視点だと謎は深まるばかりです。
ハイド、自害する
ジーキル宅の執事がアタスンに助けを求めてきました。本物の主人はすでに殺害されており、ハイドと入れ替わっているのではないか、というのです。
強行突破をはかると、書斎の中には絶命したハイドが。一方、ジーキルの遺体はどこにも見当たりません。そして現場にはアタスン宛ての手紙が残されていました。
最後に、ラニョンの手記とジーキルの陳述書を通して一連の事件の真相が明かされます。
これは夏目漱石の『こころ』でも用いられている構成ですね。ちなみに、漱石はスティーヴンスンを好きな作家のひとりに挙げています。
ハイドの正体
衝撃の事実
ラニョンの目の前で調合した薬を飲み、変身したハイド。その正体は、なんとジーキルだったのです!
……まあ、知ってましたけどね。
ジーキル=ハイド。それが当前のようにあちこちで語られているので、私などは「倒叙ミステリー形式の小説なのかな?」なんて思っていました。実際に本作を読んでみると、なかなかハイドの正体が発覚しないので、逆にびっくりしたくらいです。
このような過去の経験から、本記事ではなるべく順を追ってストーリーを紹介してみようと思い立ったのですが、いかがでしたでしょうか。
ただ、真相を知ったうえで読んだとしても、本作の魅力が損なわれることはありません。スリリングで目が離せない展開にぞくぞくすること請け合いです。これぞストーリーテリングの妙。
二元的存在としての人間
資産家の家に生まれ、才能もあり、努力のできる人間だったジーキル。恵まれた環境にあった彼ですが、快楽に対して強い欲望を持っているという欠点を抱えていました。
紳士ジーキルとしての体裁を保ちつつ、裏ではハイドとして享楽にふける。快楽の代行者として生み出されたハイドが非道徳的・悪魔的存在なのは、ジーキルの理想が高すぎる反動でしょうか。
普段は真面目なのに飲酒等でたがが外れて暴れ出したりする人のもっとひどいバージョンというか、表向きには高潔な人物として振る舞っていた分、人格の振れ幅が大きかったように思われます。
純粋悪
ハイドに対して言い表しがたい奇妙な印象を受ける目撃者たち。その理由についてジーキルは、一般人は「善と悪の混合体」であるのに対し、ハイドは「純粋な悪」だからではないか、と考察しています。
ここで注意しなければならないのは、ジーキルのほうは依然として「善と悪の混合体」であるという点。岩波文庫のあとがきによると、作者は「ジーキルの破滅はむしろ彼の偽善に帰すべきである」と手紙に書いたそうです。
しかし自制できているのであれば、たとえ偽善者であろうが、「善」に分類されてよいのではないか、と思います。普通の人でもよからぬ考えが頭によぎる瞬間はあるでしょうが、それを実行に移すのと移さないのとでは大違いですから。
ただジーキルは、悪行三昧のハイドと記憶を共有しているにもかかわらず、見て見ぬふりをしてきました。そうしようと思えば、もっと早くハイドを止める(断薬する)ことができたというのに。
逆転
体格のよい中年男性であるジーキルに対し、ハイドが小柄で若いのは経験値不足だからではないか、というのがジーキルの仮説です。実際、時間の経過とともにハイドは力をつけていきました。
やがて就寝中に勝手にハイド化するようになり、ついにはジーキルの姿を維持するのに苦心する事態にまで陥ってしまいます。
ハイドにじわじわと侵食されていくジーキルの描写は、怪奇小説としての真骨頂。偶然の産物であった薬の在庫が底をついたのが運の尽き。本来のジーキルの人格はそこで消え去ったようです。
もっとも、ハイドになっているときの精神状態については、ジーキルの証言からしか知ることができません。ジーキルの自我は、厳密にはどこまで残っていたのか? 生に対する執着心が強いハイドが自ら死を選んだ、という点がやや気にかかります。
アタスンの性格上、陳述書の内容を安易に口外したりはしないでしょう。それを見越して、自殺という最後の大罪もハイドに押し付け、“稀代の悪党に金銭だけでなく命まで奪われてしまった哀れな紳士”と世間に思われるのであれば、それはジーキルにとって都合のよい筋書きなのでは?なんて意地悪な見方をしてしまいました。
表と裏、光と影
天使のごとき人格が出現していた可能性についてジーキルが書き残しているように、薬は厳密には悪を分離するものではなかったことが示唆されています。薬の効果は人間が内に秘めた性質を解き放つことであって、ジーキルの場合はそれが邪心であった、ということです。
これまでにも見てきたとおり、ジーキルはかなりメンツを気にするタイプです。ハイドの姿から元に戻れなくなってラニョンを呼び出したときには、「命」「理性」と並べて「名誉」に関わる状況だと述べていました。また陳述書でも、ハイドとして行った悪行の詳細については触れていません。
しかしこれは、ジーキルの性格の問題だけではなく、彼の社会的立場や時代背景も影響しているのでしょう。
ジーキルの屋敷から見える街の風景は、彼の表の顔・裏の顔を象徴しているかのように、正面玄関側と裏口側で雰囲気が全く異なっています。本作は一個人の二面性だけでなく、当時の都市の光と影、臭いものに蓋をするような社会を風刺しているのかもしれません。
おわりに
二重人格の代名詞として知られる本作ですが、善と悪の対立という以上に理性と欲望の対立を描いているように思います。
ジーキルとハイドほど極端でないにせよ、人間は多面的な存在です。「悪」だけ分離するなんてできませんし、それゆえに「善と悪の混合体」として上手くバランスをとって生きていくことが大切なのでしょうね。