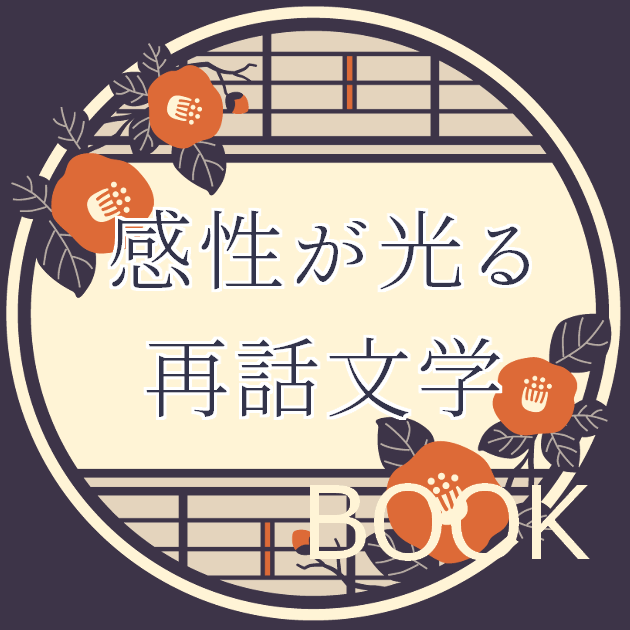新潮文庫『小泉八雲集』(上田和夫訳)は小泉八雲/ラフカディオ・ハーン(1850-1904)の代表作を収めた短編集です。
今回は、その中から個人的に印象に残った怪談・奇談を紹介しています。
『小泉八雲集』
耳なし芳一のはなし(『怪談』より)
平曲を得意とする琵琶法師の芳一が、さる貴人の依頼を受け、夜な夜な弾き語りを披露することになるが……という有名な怪談のひとつ。
芳一の目が見えないため、彼がいったいどこで誰に対峙しているのか、最初のうちは読者にもよくわかりません。その後、不審に思った寺男が芳一を尾行した結果、ようやく異常な状況が明らかになるのです。
改めて読んでみて、本作のホラーとしての構成の秀逸さを再認識しました。
と同時に、耳にお経を書き忘れたのは和尚さんではなく手伝った小僧さんであり、長年にわたり勘違いをしていたことに気がつきました。濡れ衣を着せていたようで申し訳ない。
ただ和尚さん本人も反省しているように、確認不足がとんでもない結果を招いたのは間違いないですが。ダブルチェックって大事。
雪おんな(『怪談』より)
2人の木こりのうち年若い巳之吉(みのきち)を哀れに思い、彼を見逃した雪女。翌年、彼女は「お雪」という名の旅人として姿を現し、巳之吉と結婚します。
逆に考えると、茂作じいさんは若くもなければ、雪女の好みでもなかったので助けてもらえなかったのでしょうか。なんだか不憫。
物語の結末は、雪の情景とあわさって悲しくも美しいイメージを喚起しますね。約束を守らなかったために破局を迎えるという異類婚姻譚の代表例です。
ろくろ首(『怪談』より)
出家した元侍の回竜(かいりょう)は、甲斐の国(現在の山梨県)を行脚中、親切な木こりに出会い、彼の家に泊めてもらうことになりました。しかし、これは罠だったのです。
そこにいた5人の男女の正体は、人間を食べる化け物「ろくろ首」。本作に登場するろくろ首は、首が長く伸びるタイプではなく、頭部が胴体から分離して飛び回るタイプです。
普通の人間であれば命からがら逃げ出すのが精一杯なのでしょうが、回竜は違いました。
彼の胆力と怪力がすごすぎて、ろくろ首があまり怖くない……むしろ回竜のほうが怖いくらいかもしれません。何しろ生首(化け物のボスの頭)を袖にぶら下げたまま旅を続けるのですから。
私は武蔵坊弁慶のような豪傑を想像しながら本作を読みました。
果心居士(『日本雑記』より)
逃げ出した絵
主人公は果心居士(かしんこじ)と呼ばれるおじいさん。彼は地獄の様子が描かれたすばらしい掛け物を持っており、それを人々に見せては説教をすることで生計を立てていました。
あるとき、織田信長がその掛け物を所望しますが、果心居士は金百両と交換でもなければ難しいと断ります。
信長の家臣のひとりである荒川は、老人を斬り捨て、掛け物を奪うという暴挙に出ました。すると、なぜか中身が白紙になっており……。
色あせた魅力と消えた幻術師
本作は、絵がモチーフなだけあって頭の中に映像が浮かびやすく、また含蓄に富んだ物語です。
本当に優れた絵には意志があり、正当な所有者から離れようとしない、というのが面白いポイントのひとつ。この話を聞いた信長は、今度は百両を払って掛け物をちゃんと買い取ることにしました。
ところがどうしたことでしょう。所有権が移った途端、絵が以前ほど魅力的に見えなくなってしまったのです。それまではプライスレスだったのが、値段をつけたことでそれ相応の品質になったとさ、というオチ。
加えて、果心居士が一貫して飄々とした雰囲気なのがユーモラスで、ラストの退場の仕方もお見事の一言に尽きます。
『小泉八雲東大講義録』
英語の教師として
小泉八雲は約7年間、東京帝国大学で教壇に立ち、英語の講義を行っていました。
その人気の反動で、後任の英文学講師である夏目漱石は学生たちに講義をボイコットされる事態になったんだとか。今聞くとぜいたくな話に思えますし、両方受講できた学生さんがうらやましい。
さて、そんな講義録のうち16篇が訳出・収録されているのが角川ソフィア文庫『小泉八雲東大講義録 日本文学の未来のために』(池田雅之編訳)です。
以下では先述の怪談と絡めて、『講義録』第2章から「文学における超自然的なものの価値」の節を紹介します。
文学における超自然的なものの価値
八雲はまずghostlyという英単語について説明していますが、これが思いのほか包括的な意味を持っているのです。「霊的なものには、必ず真理の一面が反映されている」ため、人間の関心は尽きません。
こうした偉大な芸術作品と霊的な存在にまつわるテーマは、「焼津にて」(次の記事を参照ください)でも登場していました。
また、八雲の怪談は「再話文学」とよばれ、昔話や伝承を原典どおり書いたものではありません。物語としてのわかりやすさや独自性、文学性を付与しています。読者の恐怖心をあおり、想像力を刺激する演出や構成、人間ドラマなどですね。
『講義録』を読むと、こうした執筆活動を支えている背景も垣間見えて、そういう面でも感心します。
霊的なものと夢
英語で書かれた怪奇小説のうち八雲一押しなのがブルワー・リットンの『幽霊屋敷』。リットン作品における悪夢の再現度がいかほどのものかという点を掘り下げていますので、ぜひ『幽霊屋敷』本編とあわせてお楽しみください。
また、八雲は夢物語の例として日本の「果心居士」も挙げています。この話は私もお気に入りなので、上で内容を詳しめに書きました。
このほか、八雲はドイツの作品『ウンディーネ』などにも話を広げています。空想と現実の組み合わせの妙こそが、芸術性の高さにつながるというのです。
夢は恐怖だけでなく、「美しい霊的な優しさ」も供給してくれるもの。この「根源的な文学の源泉」としての夢談義は非常に面白かったので、おすすめです。
※次の記事では、小泉八雲の随筆・日本文化論等を紹介します。そちらもご一読いただけますと幸いです。