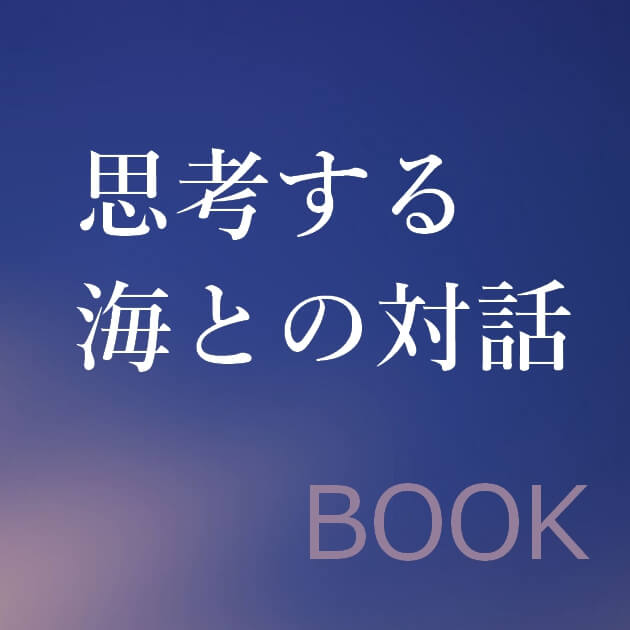あらすじ
これは、現在では高野山の大和尚として知られる旅僧・宗朝が語った昔話である。
若い時分、飛騨の山越えをしようとしたときのこと。危険な旧道に入った薬売りの男を連れ戻そうと、宗朝はその後を追った。
山中で蛇や蛭(ひる)に遭遇し、すっかり疲れ果てたところで一軒の山家(やまが)にたどり着く。そこには妖艶な女主人が住んでおり……。
主な登場人物
「私」
若狭へ帰省するために乗った汽車の中で上人(しょうにん)と出会う。寝つきが悪く、何か面白い話をしてほしいと上人にせがむ。
宗朝(そうちょう)
高野山に籍を置く旅の上人。歳は40代半ばほどで、温厚かつ気さくな人柄をしている。若い頃の奇妙な体験を「私」に語って聞かせる。
富山の薬売り
鼻持ちならない下衆な男。宗朝を追い抜き、山深く入り込んでしまう。
婦人(おんな)
容姿端麗な女性。上品で親切な人物だが、時折不審な言動が見られる。
次郎
子どもっぽい太った若者。病のため足が悪く、また日常会話もままならない。婦人の亭主らしいが……。
親仁(おやじ)
婦人を「嬢様」と呼ぶ、使用人らしき男。市場に馬を売りに行くため一晩留守にする。
内容紹介と感想
旅は道連れ
「私」が道中を共にすることになったのは、高野山の上人でした。
その独特の語り口は、落語家や講談師をイメージさせ、実に話上手。それもそのはず、彼はなんと宗門名誉の説教師だったのです。
このように偉いお坊さんである宗朝ですが、気取ったところは一切なく、どことなく飄々とした雰囲気を感じます。トルコ帽のようなものをかぶっているなど、服装もあまりそれらしくはありません。
命が惜しくて川の水の安全性が気になったり、いやな奴だと思いつつも薬売りを追いかけたり、その後大嫌いな蛇に出くわして、そうとわかっていたら「地獄へ落ちても来なかったに」とめそめそしたり、過去のエピソードを見てもその率直な性格に好感が持てます。
分け入っても分け入っても青い山
さて、聞かっしゃい、私はそれから檜の裏を抜けた、岩の下から岩の上へ出た、樹の中を潜って草深い径をどこまでも、どこまでも。
現在の時間軸で、「私」と上人は汽車を利用した近代的な旅をしています。季節は雪がちらつく冬、北陸地方の宿で会話が交わされます。
一方、回想の中の上人はと言えば、夏の飛騨山中を徒歩で進んでいるのです。種田山頭火の句そのままの世界ですね。現在の冬景色との対比により、青々とした山々の光景がより鮮明な姿で立ち現れてきます。
絶妙な時代背景もいいですよね(本作が発表されたのは1900年)。一昔前、山奥深く這入って行けば、昔話に出てくるような山姥だのに遭遇するかもしれない、と思えた時代。山を異界として見ていた時代です。
夏山の一夜
蛇や蛭をやり過ごし、森を抜け、坂を越え、もうこれ以上は歩けない……というところで、馬のいななきが聞こえてきます。驚いたことに、こんなところに一軒家が。
美しい婦人が出てきて、旅籠があるのはまだまだ先だと言うので、宗朝はここで一晩お世話になることになりました。作中の情報を踏まえると、この婦人の年齢は三十歳くらいですかね。
婦人の案内で崖下の水場に向かう宗朝。ここで、婦人は手ずから宗朝の背中を流してくれました。非常にドキドキするシーンですが、邪魔が入ります。
ヒキガエルにコウモリ、猿といった動物たちが次々に婦人にちょっかいをかけてくるのです。「畜生、お客様が見えないかい」「お前たちは生意気だよ」と、婦人は思わず怒りをあらわにします。魔女と使い魔のようで、私だったらこの辺でお暇したいところです。
当の宗朝は、はしゃぎ過ぎた子どもを叱る若い母親のようだ、という印象を抱きます。「優しいなかに強みのある、気軽に見えてもどこにか落着のある、馴々しくて犯し易からぬ品のいい、いかなることにもいざとなれば驚くに足らぬという身に応のあるといったような風」である、と。
宗朝はそのまま夕飯をごちそうになって一泊するのですが、夜半またしても獣の気配を感じ、陀羅尼(呪文)を唱えて過ごします。
真相
翌日、いったんは山家を離れたものの、滝の前で思いを巡らせる宗朝。すっかり婦人が不憫になってしまっていたのです(個人的には、ここで暮らすようになった当時まだ子どもであったことや、婦人の父親でもある医者にひどい手術をされたことから、次郎の方により同情しますが)。
彼女を支えるため、この山で骨をうずめる覚悟をしかけていたちょうどそのとき、親仁が帰ってきました。
そこで衝撃の事実が発覚します。
並の人間であれば、昨日水場に行った時点で畜生に代わっていたはずだ、と言う親仁。そう、昨日見かけたヒキガエルや猿たちはすべて人間の成れの果てであり、親仁が連れていた馬こそが薬売りだったのです。
さらに親仁は、婦人が身内や帰る場所をなくした経緯を語ります。しかしながら、今では自ら進んで世間との関わりを断っている色好みな女なので同情無用、今回は運よく見逃してもらったのだから、余計なことは考えずさっさと出発してしまいなさい──そのようなことを言い残し、親仁は去っていきました。
鬼女か聖女か
それにしても、宗朝はなぜ無事でいられたのでしょうか。仏教説話として見るのであれば、仏様のご加護があったおかげ、で済ませてもよいのかもしれませんが。
「感心に志が堅固じゃから助かったようなもの」というのが親仁の意見です。
私自身は、宗朝の裏表のない性格がよかったのかなあと思います。冒頭でも述べましたが、彼は怖いものは怖いと言い、美しいものは美しいと言う率直な人です。次郎に手厚く接する婦人の姿を見て、感極まり涙をこぼしたときなどは、婦人も心を打たれたのか、「貴僧はほんとうにお優しい。」と言ったほどなのです。
婦人は婦人で、単純に毒婦の一言で切り捨てることはできません。「毒にも薬にもならぬ」ということわざがありますが、その逆で、いうなれば「毒にも薬にもなる女」ではないかと思うのです。
十年以上前、まだ里に住んでいた頃の彼女が患者に触れるとけがや病気が癒えた、という逸話などは、まるで聖女のようではありませんか。
次郎との関係では、とりわけ情の深さや母性を感じさせます。次郎を見捨てようと思えばいくらでもできたでしょうが、そんなことはせず、婦人はずっと彼の世話をし続けています。この二人は、夫婦というより年の離れた姉弟といった雰囲気です。
また、宗朝に可憐な白桃の花にたとえられた際、少女のように喜んでいた一幕も印象的です(ちなみに桃は、女性に対する敬意の象徴・多産の象徴とされ、その花言葉はチャーミング・私はあなたのとりこ・天下無敵・長命などだったりします)。
薬売りら他の男たちが見せたであろう邪な気持ちを、婦人が宗朝から感じ取ることはなかった──すなわち、邪心には邪心で、真心には真心で応えたというだけの話だったのかもしれません。
おわりに
上人は特に教訓めいたことは語らず出立し、「私」がどのような感想を抱いたかについても掘り下げられることはありません。
このさらりとした締め方は、私が本作を好きなポイントのひとつです。『高野聖』の物語から何を読み取るのか、それは読者一人一人に委ねられているのではないでしょうか。