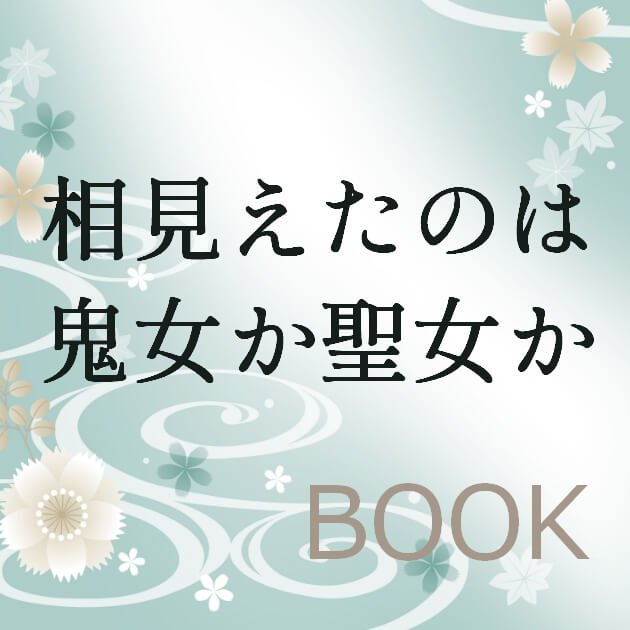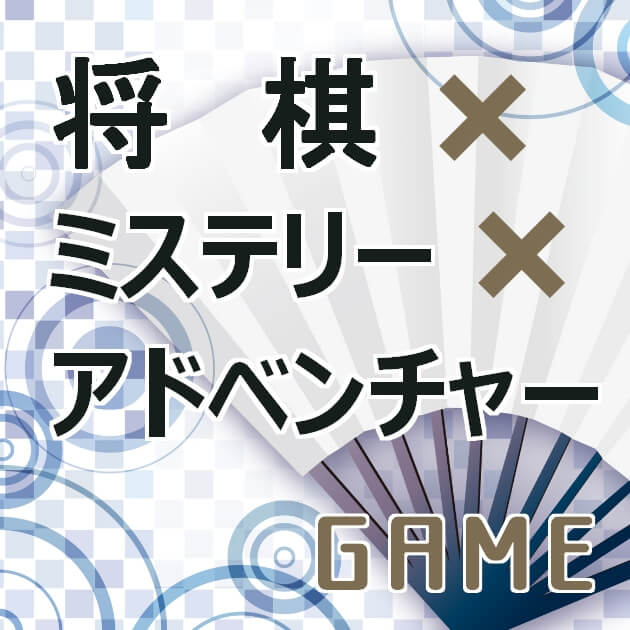近現代文学史における著名作家とその作品を紹介するページです。(随時更新)
江戸川 乱歩(1894-1965)
代表作:明智小五郎シリーズほか
国内における探偵小説の先駆者。『怪人二十面相』等の子ども向けシリーズも人気ですね。ペンネームは、近代探偵小説の原型をつくったとされるエドガー・アラン・ポーからとられています。
金田一耕助シリーズで知られる横溝正史とは、友人兼ライバルの間柄です。
〈作品紹介〉
『押絵と旅する男』(1929)
私が夜汽車で出会ったのは、押絵に話しかける奇妙な男で……。幻想的な雰囲気の漂う一篇です。
〈関連サイト〉
- 江戸川乱歩館(三重県鳥羽市)
- 立教大学大衆文化研究センター/旧江戸川乱歩邸(東京都豊島区):東京で20回以上の引越しを繰り返した乱歩。その最後の住まいは、現在立教大学に移管されています。
宮沢 賢治(1896-1933)
代表作:『春と修羅』『注文の多い料理店』ほか
独創性に富んだ作風で知られる童話作家・詩人。盛岡高等農林学校(現・岩手大学農学部)の卒業生で、農業指導と並行して創作活動をしていました。終生日蓮宗を信仰しており、作品にも影響が見られます。
〈作品紹介〉
『銀河鉄道の夜』
孤独な少年ジョバンニと友人カムパネルラが、銀河鉄道に乗って星の世界をめぐる幻想的な物語。作者の没後に発見・出版された小説で、決定稿のない未完の名作です。
〈関連サイト〉
- 宮沢賢治記念館・イーハトーブ館・童話村(岩手県花巻市)
- もりおか啄木・賢治青春館(岩手県盛岡市)
- 石と賢治のミュージアム(岩手県一関市):賢治は鉱物の採集が趣味で、子どもの頃は「石っこ賢さん」と呼ばれていたほどでした。
尾崎 翠(1896-1971)
代表作:『こほろぎ嬢』『第七官界彷徨』ほか
鳥取生まれの小説家。『第七官界彷徨』が再発見された後、あらためて注目を集めるようになりました。
〈作品紹介〉
『歩行』『地下室アントンの一夜』(1931・1932)
ヒロイン小野町子を巡る恋愛模様を綴った連作短編。想い人のことを忘れようと努める少女の葛藤と、その少女に恋する若者の詩人としての危機が描かれています。
〈関連サイト〉
井伏 鱒二(1898-1993)
代表作:『山椒魚』『黒い雨』ほか
尊敬する森鴎外に似たかっちりした文章に加え、庶民寄りの目線が特徴です。
私が昔よく読んでいた『ドリトル先生』シリーズの訳者でもあるという事実に気がついたのは、大人になってからのことでした。
〈作品紹介〉
『ジョン万次郎漂流記』(1937)
直木賞受賞作品。リアリティあふれる歴史小説で、幕末から明治にかけて活躍した国際人・中浜万次郎の波乱万丈な人生を精緻に描き出しています。
〈関連サイト〉
- ふくやま文学館(広島県福山市):常設展示に「井伏鱒二の世界」があります。
横光 利一(1898-1947)
代表作:『日輪』『機械』ほか
川端康成とともに雑誌「文芸時代」を創刊、新感覚派として文学運動を行いました。のちに新心理主義に転回。
〈作品紹介〉
『日輪』(1923)
邪馬台国成立前夜の物語。卑弥呼と彼女をめぐる王たちの攻防を描いており、独自の卑弥呼象は読み手に新鮮な印象を与えます。
『機械』(1930)
「四人称の設定」を取り入れた、新心理主義路線の実験小説。小林秀雄が「世人の語彙にはない言葉で書かれた倫理書だ」と評した短編です。
〈関連サイト〉
川端 康成(1899-1973)
代表作:『伊豆の踊子』『雪国』『山の音』ほか
日本人初のノーベル文学賞受賞者。長編小説だけでなく、「掌(たなごころ/てのひら)の小説」と呼ばれる短編も数多く書いています。
〈作品紹介〉
『古都』(1961~62連載)
祇園祭の夜、呉服問屋の一人娘・千重子は自分に瓜二つの村娘・苗子と出会い……。異なる環境で生きてきた双子姉妹の運命と、京都の四季折々の美しさを描いた抒情的な作品。
なお、川端は画家の東山魁夷と親交があり、文化勲章受草記念に「冬の花」、ノーベル文学賞受賞記念に「北山初雪」と題した絵を贈られています。北山杉をモチーフとする「冬の花」は、『古都』の章タイトルにちなんでいるのだそうです。
【参考】川端康成『古都』あとがき(新潮文庫)
〈関連サイト〉
梶井 基次郎(1901-1932)
代表作:『檸檬』『城のある町にて』ほか
20歳の時に発病した肺結核は、その後の生活や文学活動に大きな影響を及ぼしました。療養先の伊豆湯ヶ島温泉では、川端康成や萩原朔太郎、宇野千代らと知り合うことに。
鋭い感性が光る梶井の作品群は、死後に高い評価を受けるようになります。
〈作品紹介〉
『Kの昇天』(1926)
月夜の海で、Kはなぜ溺死するに至ったのか? 月や影・ドッペルゲンガーを扱っており、幻想的な要素の見られる作品です。
『闇の絵巻』(1930)
湯ヶ島時代の体験を素材とした短編小説。湯本館滞在中の川端康成を訪ねた帰り道の様子がベースとなっています。
中島 敦(1909-1942)
代表作:『山月記』『李陵』ほか
儒学者の家系で幼少時から漢学に親しんで育ちました。国語の教科書でおなじみの『山月記』以外にも、中国古典を題材とした作品が多く見られます。
〈作品紹介〉
『悟浄出世』『悟浄歎異』(1942)
自意識過剰でネガティブなインテリ・沙悟浄を主役に据えた西遊記異聞。『山月記』の李徴同様、沙悟浄にも作者自身の内面が反映されていると考えられます。
『文字禍』(1942)
古代メソポタミアの図書館で、文献を調査していた老博士は奇妙な体験をし……。初期短編の一つで、一般にゲシュタルト崩壊として知られる現象が登場します。文字媒体が人間に及ぼす影響について書かれており、古代を舞台にしているものの、テーマは非常に現代的です。
〈関連サイト〉
- 神奈川近代文学館(神奈川県横浜市)「中島敦文庫」をコレクションとして保存しています。
加藤 道夫(1918-1953)
代表作:『なよたけ』『思い出を売る男』ほか
劇作家。代表作の戯曲『なよたけ』は、作者の存命中に完全版が上演されることはありませんでした。
なお、加藤道夫が強く影響を受けた人物には、フランスの作家ジャン・ジロドゥーのほか、民俗学者・折口信夫がいるそうです。そう言われてみれば、『なよたけ』は『死者の書』と似た雰囲気があるようにも思います。
〈作品紹介〉
『なよたけ』(1946)
『竹取物語』が生まれた過程にスポットライトを当てた作品。竹の精のように美しい少女「なよたけ」に恋をした文学青年・文麻呂は、ついには身を亡ぼすことに……。