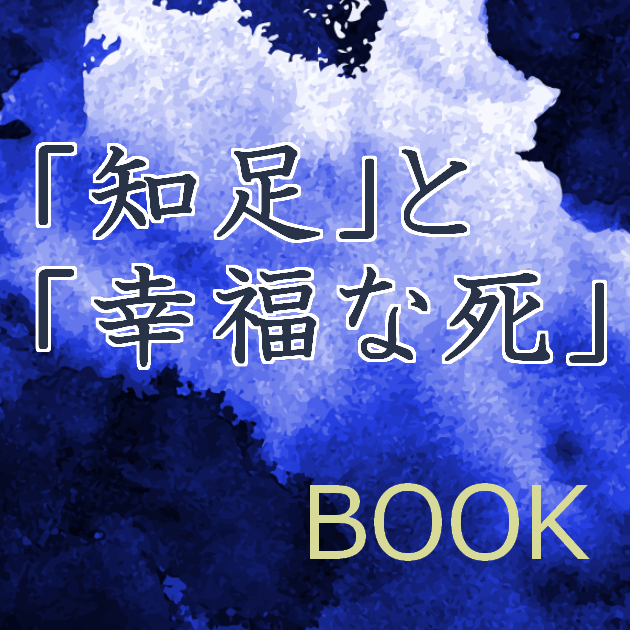あらすじ
桜舞う夕べのこと。この日、高瀬舟に乗せた罪人・喜助には奇妙なところがあった。弟殺しの咎で罰せられたというのに、その表情は実に晴れやかなのだ。同心の庄兵衛は、たまらず事情を尋ねるが……。
作品が生まれた経緯
『高瀬舟』が生まれた経緯は、『高瀬舟縁起』に詳しく書かれています。鴎外は、江戸時代の随筆集『翁草(おきなぐさ)』から本作の着想を得たそうです。
『翁草』にあるエピソード「流人の話」を読み、鴎外はそこに二つの大きな問題が内包されていると考えました。すなわち、一つは「財産というものの観念」、もう一つは「死にかかっていて死なれずに苦しんでいる人を、死なせてやるという事」です。
後述するように、前者の描写には「知足(ちそく)」という考え方が根底にあると思われます。『老子』の「知足者富(足るを知る者は富む)」に由来する言葉です。
また後者に関しては、現代医学における「ユウタナジイ」(euthanasie:一般に「安楽死」と訳される。語源は「幸福な死」)の問題に通じる点に興味を引かれたとのこと。鴎外は医者でもありましたから、そういった方面に造詣が深かったのでしょうね。
内容紹介と感想
珍しい罪人
時は江戸時代、白河楽翁(松平定信)が活躍していた頃のお話。舞台となる高瀬舟は、遠島(島流し)を申し渡された罪人を乗せて高瀬川を下り、大阪方面へ向かう小舟のことです。京都町奉行の同心(下級役人)である庄兵衛は、この舟で護送係をしていました。
ちなみに当時の刑罰レベルとしては、追放(距離は罪の重さによる)と死罪の間が遠島。誤って人を殺めてしまった場合などに適用されていたようです。
そういう背景もあってか、高瀬舟に乗る罪人には訳ありの者が多く、大抵はひどく気の毒な様子をしていました。ところが、この日連行することになった喜助という男の態度には奇妙な点があり、庄兵衛は不審に思います。
それは喜助の顔が縦から見ても、横から見ても、いかにも楽しそうで、もし役人に対する気がねがなかったなら、口笛を吹きはじめるとか、鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。
喜助の楽しげな様子が気になって仕方ない庄兵衛は、とうとう本心を問いただしてみることにしました。
知足なるもの(1)
幼少時に両親を亡くし、住所不定でその日暮らしをしていた喜助。頑張って稼いだお金も右から左へとなくなっていました。
そんな彼にしてみれば、たとえ島流しという形であっても、ひとところに腰を落ち着けられるようになり、さらに手当としてもらった二百文を貯蓄にまわせることが、この上なく嬉しいのです。また、勾留中は仕事もせずに食事を提供してもらうことが申し訳なかった、と喜助は語ります。
それほど悲惨な状況に置かれていたとは。犯罪者になった後の方が、生活環境が向上するとは。弟殺しを掘り下げる以前の段階で暗澹たる気持ちになってきます。
また現代でも、住む場所と食事を確保しようと、刑務所に入ること自体を目的として軽犯罪に手を染める例があると聞きます。そう考えると、喜助の話は遠い昔の出来事では済まない問題なわけで、一層複雑な心境になります。
知足なるもの(2)
額面の違いはあれど、給料を右から左へ人手に渡すという点においては、自分の暮らしも喜助と大差ないのかもしれない、と庄兵衛は思案します。作中の庄兵衛の考えを読むと、喜助の境遇は存外他人事ではない、とみなさんも感じるのではないでしょうか。
ただ不思議なのは、喜助が「欲のないこと、足ることを知っていること」、すなわち先に述べた知足を心得ているということです。
人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食ってゆかれたらと思う。万一の時に備えるたくわえがないと、少しでもたくわえがあったらと思う。たくわえがあっても、またそのたくわえがもっと多かったらと思う。かくのごとくに先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏み止まることができるものやらわからない。それを今目の前で踏み止まって見せてくれるのがこの喜助だと、庄兵衛は気がついた。
人間の欲望には果てがないもの。現状に満足できず、まだ不安だ、まだまだ足りない、と求めてしまうのですね。しかし喜助は違う。庄兵衛は喜助に対してある種の敬意を抱き始めました。
幸福な死とは(1)
さらに話を聞くと、喜助の弟が自害を試みていたことが明らかになります。治る見込みもない病のために、これ以上兄に負担をかけたくない――そう考えた弟は、カミソリの刃を自分の首にあてました。しかし死にきれずにもがき苦しみ、まだ息があるところで喜助が帰ってきた、といういきさつだったのです。
この苦しみを終わらせたい、最後に手を貸してほしい、と弟は訴えます。そして喜助は……。
元々積極的に手をかけようとしたわけではなく、また気が動転している状況(喜助曰く、頭の中で「車の輪のような物がぐるぐる回っているよう」)でもあり、かなり情状酌量の余地があるように思われます。
喜助はその苦を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか。
結局はお上の判断に従うしかない、と考える庄兵衛ですが、やはりどうにも腑に落ちないようです。庄兵衛の疑問は、そのまま私たち読者への問題提起でもあります。
幸福な死とは(2)
喜助が逡巡している間、弟は「恨めしそうに」見ており、しまいには「憎々しい目」を向けてきました。ところが喜助が覚悟を決めると、「目の色がからりと変わって、晴れやかに、さもうれしそうに」なったのです。
歳月の流れに加え、最後に弟の希望を叶えてやったということが、現在の喜助の心中を穏やかにしているのかもしれない、と思います。
対する私はと言えば、思考停止に陥ったきり、もやもやした気分のまま。
手塚治虫作『ブラック・ジャック』には、戦地で苦しむ負傷者と接した経験から安楽死の必要性を説く医者、ドクター・キリコが登場しますが、そのように明確な立場をとれる人間は滅多にいないでしょう。
喜助はもはや彼岸に到達しているのかもしれませんが、私は夜の黒い高瀬川で溺れているような心地です。
喜助と庄兵衛
これまで述べてきたような喜助の人物像が物語の核を占めているのは言うまでもありません。しかし、同時に庄兵衛というキャラクターも非常に重要であると感じました。
喜助の話の聞き手である庄兵衛は、読者に近い立場にいます。庄兵衛の聞き手としての姿勢が素直なので、私たちも喜助の話をすっと受け入れられます。
庄兵衛が疑り深い性格で、“弟の自殺未遂は嘘だ!全部喜助がやったことだ!”などと言い出そうものなら、喜助が一転してサイコパスか何かのようになってしまうところです。テーマもぶれてしまいますしね。
つまるところ、庄兵衛が基本的に善良な人物であることが、本作の印象を大きく左右しているのだろうと思うのです。
おわりに
主題だけでなく、美しい情景描写にも感銘を受ける『高瀬舟』。短篇小説で手に取りやすいので、ぜひ一度は読んでいただきたい鴎外作品です。