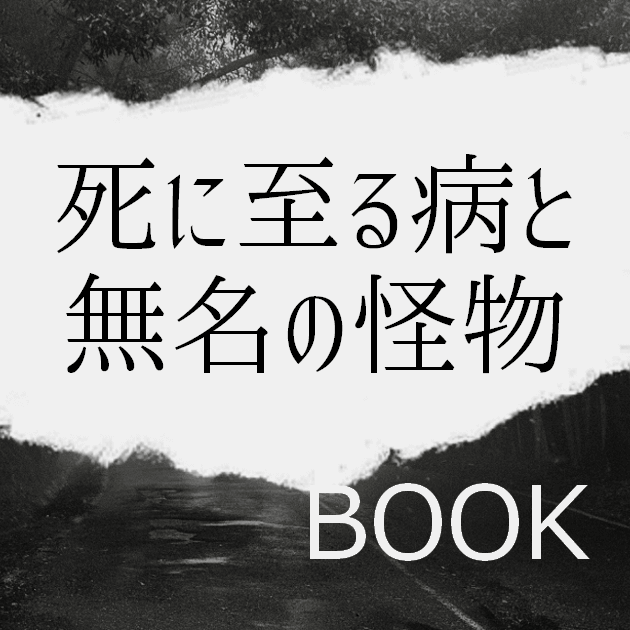今回ご紹介するのは、メキシコの作家フアン・ルルフォの『ペドロ・パラモ』(岩波文庫、杉山晃・増田義郎訳)です。
あらすじ
父親の名前も顔も知らぬまま育った「おれ」は、母ドロリータスの遺言をきっかけに両親の故郷を訪ねようと思い立つ。目的はむろん父ペドロ・パラモを探すことだ。
ロバ追いの案内で「おれ」がたどり着いたのは真夏のコマラ。奇妙なことに、そこで出会うのは死者ばかりで……。生と死、過去と現在、複数の視点が交錯する前衛的な物語。
内容紹介と感想
地獄の入り口
コマラはさびれた町というだけでなく、本当に死者が現れる文字通りのゴーストタウン。もはや生者の方が少ないくらいで、この人は本当に生きているのだろうか?という疑念が常につきまといます。
また、登場人物が多いうえに視点や時代がしょっちゅう切り替わるため、読んでいてかなり混乱しました。しかし、その独特の構成こそが本作最大の特徴なのです。
読者は、バラバラのパズルのピースをはめていくかのように、物語を読み進めることになります。
プレシアド親子
愛されなかった女
若い時分のドロリータス・プレシアドは、女性人気の高かったペドロ・パラモに結婚を申し込まれて舞い上がっていました。しかし、ペドロの本当の狙いは彼女の財産(当時、パラモ家はプレシアド家に多額の借金をしていたもよう)だったのです。
のちにペドロの横暴さに不満を募らせたドロリータスは、姉のもとへ行ったきり二度と故郷に戻りませんでした。息子にこれまで父親のことを話さなかったのも無理からぬ経緯ですね。
主人公?
物語は「おれ」ことフアン・プレシアドの一人称視点で始まるため、当初は彼が主人公なのだと思い込んでいました。
ところがなんと中盤で死亡シーンが。この地に漂う空気がよくなかったらしく、本人曰く「ささめき」(ささやき、ひそひそ話のこと)にやられた、とのこと。
行きずりの老婆ドロテアとともに埋葬され、物語後半は彼女と雑談したり、近くに墓があるというスサナ(後述)の独り言に耳を傾けたりする形での登場となります。
どんどん出番がなくなるフアン。逆に増えていくペドロやスサナの描写。結局のところ、フアンは私たち読者をコマラへいざなう狂言回しにすぎなかったのかもしれません。
ペドロ・パラモ
地元を仕切る非情なボス
「あきらめるなんて、ほかの奴にまかしときゃいいんだ。おれはあきらめるなんてごめんだよ」
メディア・ルナ一帯の大地主、通称ドン・ペドロ。上の引用からもわかるように、彼は良くも悪くも意志の強い人物です。ロバ追いのアブンディオに言わせれば「憎しみそのもの」。
父ルカスが他界した後、復讐心に燃えて大勢の人間を亡き者にし、親分風を吹かせるようになったといいます。
また、女癖が非常に悪く、その気質は息子の一人であるミゲルにも受け継がれました。基本的に人情味に欠けるペドロですが、自分のもとで育ったミゲルのことはそれなりに可愛がっていたようです。
ペドロが非情な行いばかりしているので、ミゲルが事故死した直後に気落ちしている場面がはさまれたときは、彼にも人の親としての心が一応あったんだな、なんて失礼なことを考えてしまいました(もっとも、親であるペドロよりミゲルの愛馬の方がよほどショックを受けているのではないか、と関係者から言われていましたが)。
強欲で一途な男
スサナ、おまえの帰りを三十年も待ったんだ。この日のために何もかも手に入れようとしたんだ。そう、何もかもだ。(中略)あとはおまえだけだった。
ペドロが心から愛した唯一の女性、それは幼馴染であり最後の妻でもあるスサナ。あのドン・ペドロが、スサナに思いを馳せているときだけは詩人のように感傷的になるのです。
町を出て行った彼女に会いたいがために、その父バルトロメに何度も連絡しては無視され、そうこうしているうちにスサナは他の男と結婚。スサナは未亡人になったのち、ようやくバルトロメとともに地元に戻ってきます。
衣食住を保障する代わりにスサナの身を要求するペドロ。何はともあれ、三十年も変わらぬ愛を貫いた点は評価したいところ……ではありますが、他の女性に対する扱いが散々ですしね。
また、スサナを手元に置いておくためにバルトロメを殺害するなど、手段を選ばない姿から、一部の身内以外に対して冷酷なイメージはやはり変わりません。
しかし、あらゆる物を手にしたはずの男が、どんなに執念深く待っても、どんなに深い愛情を注いでも、スサナの心はついぞ手に入れられなかったというのは皮肉な話です。
栄枯盛衰
どれもこれもペドロ・パラモの妄想と心の中のいざこざのせいなのさ。それもたかだか奥さんのスサナに死なれたからだよ。どんなに好きだったかわかるだろ?
スサナが亡くなった後のペドロは、すっかりやる気を失くして籐椅子に座ったきり。畑は荒れ放題、町はすたれ、多くの住民が去っていきました。残ったわずかな人間も〈教会派〉の戦争で兵隊にとられてしまいます。
町の隆盛と衰退はペドロのそれとそのままリンクしていました。問題行動の多かった男ですが、町にもたらしていた恩恵も大きかったのですね。そして、そんなペドロの原動力はスサナというたった一人の女性でした。
なお、訳者の杉山晃氏の解説によると、ペドロは「石」、パラモは「荒れ地」を意味するということで、コマラやペドロ自身の最期をそのまま暗示しているようです。
スサナ・サン・フアン
ドロテアの発言に「ペドロ・パラモの最後の女房」とあるので先程はそう紹介しましたが、ドロリータスとうやむやに別れたところからすると、スサナとは事実婚でしょうか。
スサナは、ペドロが「この世でいちばん美しい」「大切な人」とする愛妻である一方、「この世の女ではない」という考えが浮かんでしまうほどに、独自の世界に生きている女性。彼女は亡くなった前夫を想い続けて病んでいき、そのままこの世を去りました。
ペドロのやることなすことすべて、究極的にはスサナを手に入れるためであったとするならば、彼女はファム・ファタール(運命の女)と呼ぶに値する人物だと思います。
罪深き人々
作中の人間関係(特に男女関係)が入り乱れているのは、狭いコミュニティだからかとも思ったのですが、かなりの割合でペドロとミゲルのせいのような気も……?
思いがけずペドロの子を妊娠してしまった女性たちがいる反面、アブンディオ夫妻やドロテアなど、子どもに恵まれない人物が複数出てくるのは意図的な配置なのでしょうか。
不幸な町
田舎を懐かしんでいたドロリータスとは対照的に、スサナは生まれ育った町を嫌っていました。バルトロメも、コマラを「不幸の臭いが漂ってる町」と呼んで不快感をあらわにしています。
アブンディオが「地獄の入り口」にたとえた灼熱のコマラは、成仏できずに地縛霊のようになった人々がたくさんさまよっている土地。天国にも地獄にも行けず、不幸な町に囚われている死者たちは、生前の苦悩や過ちから逃れられないままです。
レンテリア神父
数多くいる脇役の中でも特に印象に残った人物です。ミゲルに弟の命を奪われただけでなく、姪がミゲル(らしき男)に乱暴されたことで、彼に対する恨みを募らせています。
ペドロの子どもたちの中では珍しくミゲルが父親のもとで育ったのは、レンテリア神父の口添えによるものでした。まさかこんな将来が待ち受けていようとは、当時は夢にも思わなかったことでしょう。
ペドロ親子に対する胸中は複雑ですが、レンテリア神父は金払いのよい住人の機嫌を損ねることを恐れています。そして同時に自己嫌悪にも陥っています。地獄の沙汰も金次第というか、いやな感じですね。
のちにレンテリア神父はクリステロ戦争でゲリラに参加したそうですが、どのような心境であったのか気になるところです。
アブンディオ・マルティネス
ロバ追いの男アブンディオは、当然のごとく故人。驚くべきことに、彼もまたペドロの息子なのです。
しかし生い立ちについては、嫡出子だけれど父親を知らずにコマラの外で育ったフアン、婚外子だけれど父親のそばで何不自由なく育ったミゲル、婚外子で貧しい母親に育てられたらしいアブンディオ、と三者三様。
フアンがペドロ・パラモという人物に対して抱いていた期待は、「ペドロ・パラモはとっくの昔に死んでるのさ」というアブンディオの言葉で早々に打ち砕かれました。
そんなアブンディオが再登場するのは物語の終盤。彼は愛する妻が亡くなった直後、ペドロ宅方面に向かい葬儀費用を恵んでもらおうとします。そして、ナイフでペドロを……。
フアンがコマラに向かう途中で最初に出会った人物、それも異母兄弟が父親を手にかけていた、という衝撃の事実が発覚。しかしながら、ペドロが実の息子に刺されて死亡するというラストは、これまでの行いを振り返れば因果応報のように思えます。
『ペドロ・パラモ』と『百年の孤独』
『ペドロ・パラモ』はのちのラテンアメリカ文学に大きな影響を与えました。なかでも有名なのは、ガルシア・マルケスでしょう。
ガルシア・マルケスの『百年の孤独』は、架空の町マコンドを舞台とした、ある開拓者一族の物語です。
『百年の孤独』と『ペドロ・パラモ』にはところどころ通じるものがあって、私が両作品を読んで思ったのは、ある一族や町の歴史というのは、見方を変えれば死の歴史でもあるのかもしれないな、ということでした。
ただ『ペドロ・パラモ』の場合は、死者が出てくる点を除けば非現実的な要素はあまりありませんが、『百年の孤独』は違います。現実と非現実が融合した「マジックリアリズム(魔術的リアリズム)」の特徴がより色濃く出ているのです。
たとえば、極端に長生きな人がいたり、雨が年単位で降り続いたり、美女が空に飛んでいってそれっきりだったり、『ペドロ・パラモ』と同じく死者がうろついていたり、そういったことがさらっと書かれています。
ちなみに、過去に起きた事件の詳細が徐々に明らかになっていく点などに着目すると、同じガルシア・マルケス作品でも『予告された殺人の記録』の方が『ペドロ・パラモ』に近い読後感を得られるかもしれません。
おわりに
スサナたちがコマラに帰ってきた理由は武装蜂起等で世の中が物騒になってきたからですし、レンテリア神父はゲリラに身を投じました。メキシコ史やキリスト教に造詣が深い方であれば、当時の社会情勢を踏まえてまた違った感想を持つのではないかと思います。
もっともそうした知識がなくても、情熱と冷血さの混在したペドロ・パラモという男、滅びへと向かう町に住む人々の生き死には、どこか心に残るものがあるのではないでしょうか。