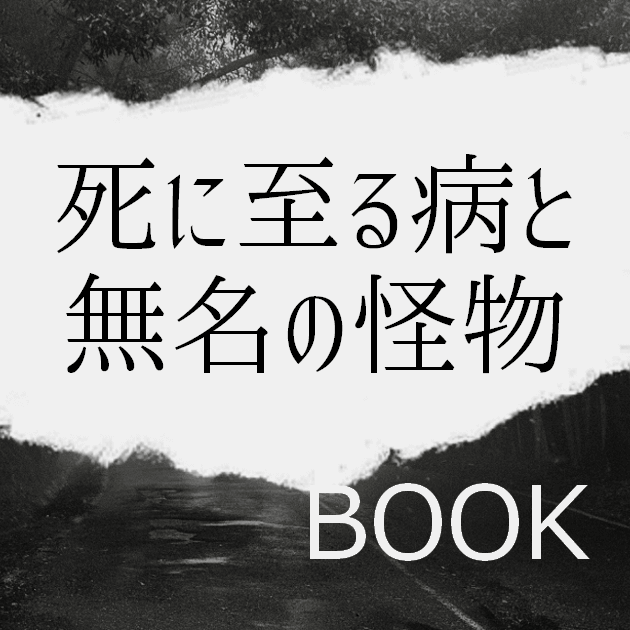1937年に発表された戯曲『白い病』(原題:Bílá nemoc)は、パンデミック下で病気や戦争に翻弄される人々の姿を描いています。
作者はチェコの作家・ジャーナリストで、SF作品『ロボット』や児童文学『長い長いお医者さんの話』でもよく知られるカレル・チャペックです。
あらすじ
物語の舞台はとある独裁国家。戦争の足音が近づきつつあるこの国で、人々は「チェン氏病」という伝染病の脅威にさらされていた。
奇妙なことに、この未知の病気──通称〈白い病〉にかかるのは45~50歳以上の人間だけであった。患者の皮膚には「大理石のような白斑」ができ、短期間で死に至る。
この状況に頭を悩ませるジーゲリウス教授。するとそこへ町医者のガレーン博士が現れた。博士は、独自開発した薬の有効性を確かめるため、大学病院で臨床実験をさせてほしいのだという。
その後、ガレーン博士は驚異的な成果を上げていく。ところが、博士は薬の製法を決して明かそうとはしなかった。より多くの人を治療するにあたり、彼にはどうしても譲れない条件があるらしいのだが……。
内容紹介と感想
以下、各登場人物に注目しながらストーリーを追っていきたいと思います。
ガレーン博士:「平和のテロリスト」
世界各地で〈白い病〉が猛威をふるう中、特効薬を発明したガレーンはまさに救世主。しかし、素直に応援できる人物かといえば、ちょっと違うのです。
人質と要求
従軍医師としての経験から戦争の悲惨さを痛感しているガレーン。彼は、国王や統治者にメッセージを伝えてほしい、と報道陣に言います。
……二度と戦争を起こしてほしくない、と。(中略)さもなければ、この病気で命を落とすことになると……(中略)もう人殺しをしないと約束するまで……私は薬を渡しません……
当然の疑問として、それまで患者を放っておくのか、と記者が尋ねると……。
では、人々が殺し合いをするのを、あなたは放っておくのか?(中略)私は政治家ではありません、皆さん、ただ医師としての義務があるのです……あらゆる人間の命を救う義務が。
子どものような純真さ、そして強情ぶり見せるガレーン。平和を願う気持ちはよくわかりますが、アプローチが独特すぎる。作者が「ある種の平和のテロリスト」「ユートピア的な脅迫者」と評するだけのことはあります。
不公平であるということ
現在、ガレーンが診察しているのは貧しい人だけ。記者は、それは富裕層にとって不公平では?と問いかけます。
ガレーンの主張はこうです。では、これまでに貧しい人がたくさん亡くなってきたことは不公平ではなかったのか? 金持ちは影響力がある、だから戦争を防ぐために働きかけてほしい、そうすれば治療する──。
確かに、死は誰にでも平等に訪れるけれど、死に至る過程は平等ではないのだろうな、とは思います。裕福であれば、大病院に入院して高額な手術も受けられることでしょう。
しかし、それでもやはりガレーンの態度には釈然としないものが残ります。
「もしも」から始まる問題提起
本作は善意や公正さについて問う、ある種の思考実験のように思われます。適切な例かはわかりませんが、私は何となくトロッコ問題を連想しました。
片方の線路の先には〈白い病〉の患者、もう一方には平和条約締結で将来的に救われる世界中の人々。すでに前者の一部にはトロッコが突っ込んでおり被害が出ていますが、後者の安全が担保されたらすぐにでもトロッコを止める(投薬する)よ、と。
作者の「前書き」によると、本作のアイデアは友人との会話の中で得た「人類の運命が自分の手に委ねられている医師のイメージ」に端を発しているそうです。
作中のような特殊な状況だからこそ、一介の医者が総統を、国を、世界を相手取って行動を起こせるわけですね。
ジーゲリウス枢密顧問官:例外は認めない(一部例外あり)
大学病院の教授ジーゲリウスは、いかなる例外も許さないという頭の固い人物です。それでいてお金や名声には弱く、お偉方は特別扱いしようとするあたり、何ともはや。
専門家向けの見学会では、臨床実験の成果を大学病院およびジーゲリウスの功績としてアピール。一方、真の功労者ガレーンは、スタッフリストに入っていないという理由で昼食さえ提供されていません。
実態は一個人の頑張りによることなのに、その手柄を横取りする上司や組織。リアルといえばリアル、なんでしょうか?
また、大学病院の第一助手は、ガレーンの特効薬を模した偽薬を使って一儲けしようとたくらんでいます。人の不安につけこむなんて嫌な商売ですが、「不安産業」という言葉を聞くくらいですし、この手の話は現実にもままあるのでしょうね。
ある家族:繰り上げ昇進からの…
時々登場する四人家族(父・母・娘・息子)の父は、軍需企業クリューク社の部長で、最近昇進したばかりです。
他人の不幸と自分の幸福
父の言動には逐一ひっかかるものがあります。次のような調子で、身近にいそうなタイプなだけに余計すっきりしません。
- 具合の悪そうなご近所さんを気にかける母に対し、その親切心のせいでうちまで感染したらどうする、と言う。
- 同僚が罹患したため部長になれた、と嬉々として話す。
- 平和だと会社が倒産する、戦争に反対するのは国益に逆らうのと同じ、と断言。
ただ、ここまで極端でないにせよ、私たちの快適な生活だって誰かの犠牲の上に成り立っている面があるのではないか……そう考え出すと、父のことを言えた義理ではないかもしれない、と自己嫌悪に陥ってしまいました。
世代間格差?
中高年だけが感染する不公平さを嘆く父。しかし、娘は「若い世代に場所を譲るためでしょ」と言い放ちます。
だって、今の若者にはチャンスがないの、この世の中に十分な場所がないの。だから、私たち若者がどうにか暮らして、家族をもてるようになるには、何かが起きないとだめなの!
突飛なことを言うなと思ったり、しかし若者にチャンスがないという点に関しては現代日本などにも当てはまるのだろうか?とも思ったり、いやいや、やっぱりこんな形は違うだろうと思ったり、読んでいて複雑な気持ちになる発言です。
診療拒否
父が昇進した直後、母の感染が発覚し、二人は診療所へ足を運びます。しかしガレーンの対応は、部長クラスなら裕福だろうし、平和活動をしてくれれば(軍需工場を辞めたりすれば)治療を考えますよ、というもの。
善良な人物という印象が強い母が診察を拒否される場面では、ガレーンのやり方に対して一層懐疑的になってしまいます。けれど、それも作者の想定内。
母のエピソードやその後のクリューク男爵の顛末を見ると、ガレーンの罪深さを思わずにはいられません。ガレーンが男爵に誠実さを求めた結果があれかと思うと……。
元帥:勝利を目指す独裁者
世界最大の軍隊を擁する独裁国家の元帥。しかし友情には厚く、娘たちの説得に応じるなど、まったく話の通じない相手でもありません。実は、本作一番の闇はまた別に存在しているのです……。
義務と権利
元帥が平和を望みさえすれば万事解決する、というのがガレーンの意見。しかし、元帥は「我が国民から勝利を奪うことは、私にはできない」と返します。元帥にしてみれば、勝利は国民の権利であり、国民を勝利に導くことが彼の義務らしいのです。
〈白い病〉に対する恐怖心が先立って世界中で反戦運動が広がっており、国内でも年配者は戦争に対して及び腰です。それでも元帥の意志は固く、若者たちの士気も高まっているというのだから恐ろしい。
宣伝大臣はメディア等を通して愛国者をあおる方法を画策しており、こうした流れも社会風刺を感じます。
開戦と発病
ついに始まった隣国への攻撃。意気揚々と演説をしていた元帥ですが、自分の胸に白い斑点を発見し、打ちひしがれます。
しかしパヴェル(クリュークの甥)は言うのです。元帥がいなくなれば混乱や内戦が生じる、あなたには戦争を終わらせる義務がある、と。
戦争推進派の中心人物がいなくなったからといって、スムーズに平和が実現するわけでもないのが難しいところ。特にこの国の場合、めぼしい後継者もいないようですし、カリスマ的支配というのは長続きしないものらしいですからね。
さらに冷静に助言を続けるパヴェルですが、元帥いわく「この若者は有能だ、だが分別がありすぎる。偉大なことはなし得んだろう」。
一理あるかも?と一瞬思ったものの、いろいろなタイプの人がいないことには世の中は回りません。偉業をなすかどうかはさておき、今後パヴェルや元帥の娘アネットが次代を担う存在になるであろうことは想像に難くないでしょう。
条約締結なるか
ガレーンから治療と引き換えに提示されたのはもちろん平和条約の締結。元帥はしばらくごねていましたが、最終的には思いやり深いアネットと思慮深いパヴェルの言葉に心動かされます。
だがあと数年生きることができれば……使命があれば、人間は多くのことを耐えられる。平和か……神は、平和を築くよう望んでいる──(中略)この世から〈白い病〉がなくなる──それは大勝利だな?
新しい勝利の形、希望の光が見え、ほっとする場面です。しかしそれも束の間、最後は……。
群集:最後に残るもの
※以下の内容には結末部分に関するネタバレが含まれます。未読の方はご注意ください。
暴徒化
場面変わって、元帥の演説後、興奮さめやらぬ様子の群集。狂信的な人々の中には、例の家族の息子もまざっています。同じ若者ではあるものの、パヴェルたちとは対照的な描かれ方です。
通りかかったガレーンが反戦を訴えると、群集は「裏切り者」「臆病者」と口々に叫びながら殴る蹴るの暴行を加え始めました。
こと切れるガレーン。特効薬の瓶をそうと知らないままに割る息子。「戦争万歳!」「元帥万歳!」という喧騒の中で物語は幕を下ろします。
結果的に、群集は彼らが英雄視している元帥の命も、そして息子に関しては母親の命も奪ったことに。戦争は終わらないし、〈白い病〉も治らない。最悪の結末です。
群集心理の恐怖
筆者は、かれの形而上学的な公正さについて、自身の罪を最終的な破局で償うことを描く以外には何もできない。
「作者による解題」によれば、このラストは必然だったとのこと。そして、「ただ残ったのは、元帥そしてその敵対者の命も同時に奪った狂乱状態にある群集のみ」。
群集心理(集団心理)の特徴としては、非合理性、精神的同質性、感情性、匿名性、無責任性、被暗示性(暗示にかかりやすくなる)などがあるらしいですね。元帥には少なくとも責任感がありましたが、暴走した群集にはモラルも何もありません。
そんな群集の姿には恐怖を覚えます。しかし、彼らも平時はきっと普通の人のはず。私自身、絶対にそちら側に行かないとは言い切れないのではないか?と思うと、別の怖さがあります。
おわりに
ストーリーに引き込まれてどんどん読み進められる反面、終始モヤモヤした気持ちになる作品でもあります。上の感想もかなり歯切れの悪い書きぶりになってしまいました。
私たち読者がガレーン博士や元帥の立場になることはまずないでしょうが、部長一家の誰かや群集の一人になる可能性は捨てきれません。本作は現代にも通用する物語であり、一読の価値があると思います。