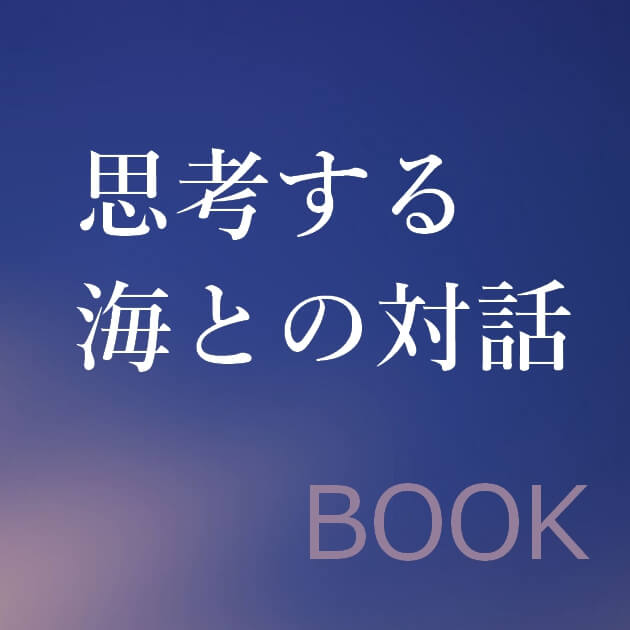『ソラリス』(旧邦題:ソラリスの陽のもとに/原題:SOLARIS)は、ポーランドの作家スタニスワフ・レムの代表作。映画『惑星ソラリス』の原作小説です。
※当記事における作中用語の表記は、すべて飯田規和氏による旧訳を参考にしています。
あらすじ
近年、惑星ソラリスをめぐる研究は停滞していた。
新たに現地に派遣された心理学者のケルビンは、異常事態を目の当たりにする。ステーション内は荒れており、研究員たちは何かに怯えているのだ。
ケルビンは調査を開始するが、途中疲労で眠りに落ちてしまう。そして目を覚ますと、そばに〈彼女〉がいた。十年前、この世を去ったはずの恋人が……。
主な登場人物
クリス・ケルビン
ソラリスに赴任してきた心理学者。十年前に起きたハリーの事件に関し、いまだに自責の念が消えずにいる。
ギバリャン
ケルビンが到着する直前に自害する。〈海〉に強力なX線を照射する計画を立てていた。
スナウト
ギバリャンの補佐でサイバネティックス学者。ひどく疲れた様子をしており、どういうわけか怪我を負っている。
サルトリウス
物理学者。実験室に引きこもっており、あまり姿を見せない。ギバリャンの計画を推し進めようと苦心している模様。
ハリー
ケルビンの恋人。ケルビンと喧嘩した後、自ら劇薬を注射して亡くなったのだが……。
内容紹介と感想
海からの来訪者
序盤からステーションには不穏な空気が漂っています。ギバリャンが亡くなった事情もよくわかりません。そのうえ、スナウトが第三者に会う可能性をほのめかしてくるのです。
何かがおかしい、誰かに見られている? 動揺するケルビンとともに、読んでいるこちらまで薄氷をふむ思いをすることに。実際、ケルビンは謎の黒人女性を目撃し、実験室からは子どもの足音や声が聞こえてきます。
そんな中、追い打ちをかけるように現れたのがハリーです。もうこの世にいないはずの、いや、いてはならないはずの女性でした。
〈考える海〉
惑星ソラリスの〈海〉は生きている──。
ソラリスの存在が知られるようになったのは、ケルビンが生まれるよりもずっと昔の話です。そして、粘着質の有機物質から構成される〈海〉は、地球人類の想像をはるかに凌駕する「思考力をもつ怪物」であることが明らかになってきました。ソラリスの〈海〉は、全体が一つの脳、一つの生物と言えるような存在だったのです。
さらに、それだけではありません。〈海〉は、人間の記憶の一部を物質化する能力さえ持っていました。
「お客」のハリー
スナウトが「お客」と呼ぶ彼女は、ハリーであってハリーでない、ニュートリノからなる影のような存在です。人間の記憶を反映した鏡像なのです。
このハリーは、自分がどこから来たのか、なぜここにいるのか、まったく把握していません。無垢な赤ちゃんのようでもあり、悪く言えば空っぽです。彼女たち「お客」に関しては、ロボットなどと同じような「不気味の谷現象」を感じないでもありません。
たとえば、カクカクしたポリゴンのような見た目であれば、一笑に付して相手にしないこともできたでしょう(また別の不気味さはあるかもしれませんが、それはおいておきます)。逆に寸分違わず本人を再現していたら、素直に受け入れられたかもしれません。
ところが実際は、甘美な夢に身を委ねようにも現実に引き戻されてしまうのです。
普通の人間なら経験に基づいて柔軟に対応できるであろうことが「お客」にはできません。キャパシティを超えると、あいまいな回答を繰り返します。決定的な人間との違いは、すぐに傷が治ってしまう超回復力を持っている点です。
これでは、かえって拒否反応が出てしまうのも無理はありません。耐えかねたケルビンはハリーをロケットに乗せて空へ発射してしまうのですが、しばらくすると何事もなかったかのように新しいハリーが顔を出します。
このハリーの立ち位置は、映画『インセプション』の主人公の妻モルと似ているのではないかと思います。ただし、あちらは完全に夢の世界の住人。こちらは醒めない悪夢、現実での出来事。だからこそ、逃げようとしたギバリャンは……。
記憶の海におぼれて
その後、ケルビンはハリーを受容する姿勢を見せるようになっていきます。ところがスナウトやサルトリウスは、〈お客〉を消し去る方向で話を進めていました。
それでもケルビンは、ハリーだけは何としても守ろうと、彼女と共存する方法を模索するのですが、スナウトに痛いところを突かれてしまいます。本当に救いたいのは、自分なのか彼女なのか、彼女だとすればどちらの彼女なのか、と。
グサッとくる台詞ですね。
今ここにいるハリーを助けたいというケルビンの気持ちに嘘偽りはないと思います。しかし、ハリー(コピー)を救うことで、過去にハリー(本物)を救えなかった自分を慰めたい気持ちがないと、どうして言えるでしょう。
ハリーはハリーで、ギバリャンの録音メッセージを聞いて自分の正体を知ってしまい、思い悩んでいます。どんどん人間味を帯びていく中で、自分を抑えようと努力する彼女の姿は非常にいじらしいのですが……。
未知との接触と新たな交流の形
ケルビンのつらさもよくわかります。それでも、振り返ってみれば、スナウトは終始「いい人」でした。冷徹なようで、本質をとらえた発言が多かったと思います。シニカルだけれど好きなキャラクターです。
それにしても、頭の中をのぞかれてしまうとは本当に怖いですね。深く刻み込まれた記憶を具象化してしまうなんてひどい嫌がらせだ、と人間の側はつい考えてしまいます。しかし、結果的にそうなっているだけで、〈海〉にそんな意図はいっさいないのでしょう。
〈海〉の行動原理に関する解釈としては、作中でいくつか意見が出ていますが、個人的に幼児のイメージというのが一番しっくりきました。
初めて見るものに対する好奇心ととまどい。〈海〉の反応には、対象物を触ったり口に入れたりする小さな子どものようなところがあります。
しかしそのような見方をするのも、人間の理解できる範囲に無理に収めようとしているだけのことなのかもしれません。人間同士でも自分の常識を相手に押し付けてしまうことがありますが、ここソラリスでは相手はまったく未知の存在なのです。
終盤、ケルビンは直接〈海〉に会いに行きます。
不思議なコミュニケーションをとる〈海〉と対話を重ねることで、これからどのような変化が訪れるのでしょうか。新しい世界が開けるのか、それとも……。想像の余地を残した形で物語は幕を下ろします。
日本語訳について
古くからある飯田規和訳『ソラリスの陽のもとに』は、原典を一部カットしているロシア語版をもとにしていました。対して、現在一般的に流通している沼野充義訳『ソラリス』は、ポーランド語で書かれた原典に基づく新訳です。
このため両者には、訳者による個性の差だけでなく、完訳かそうでないかという大きな違いがあります。これから本作を読もうと考えていらっしゃる方は、ご注意ください。
映画『惑星ソラリス』
1972年製作。監督・脚本はアンドレイ・タルコフスキー。2014年の「SF映画ベスト100(100 Best sci-fi movies)」(参考:映画.com)で第17位にランクインするなど、高い評価を受けている作品です。
原作とは構成が異なり、冒頭のケルビンは宇宙に出発さえしていません。両親の家で、かつてソラリス探検隊のメンバーであったバートンから直接話を聞く機会を得るのです。
原作ではほとんど話題に上ることのなかった両親ですが、映画では特に父親との関係性が強調されており、相対的にハリーの印象が薄まってしまった感があります。
せせらぎの音、古風な家のたたずまいなど、五感に強く訴えてくる表現は映像作品ならではで、とりわけ原風景や郷愁といったものに焦点が当てられているように思いました。
全編にわたって雲の上を歩いているような独特の浮遊感を味わうことができ、一つの作品として見た場合の完成度は非常に高いと言えるでしょう。ただし、原作と比べると感傷的過ぎるきらいがあり、人によってはそのあたりが気になってしまうかもしれません。
私が引っかかったのは、ラストシーン。とらえようによってはホラー風味です。原作のその後の展開として、あのような未来が訪れる可能性もなくはないのでしょうが。
それから、もっと単純な感想を述べさせていただくと、SF要素がより際立っているのは原作である、という点が挙げられます。映画は映画で面白いんですけどね。ここは視聴者の好み次第だと思います。
おわりに
人間の潜在意識をトレースして実体化するソラリス。非常に不安をあおられると同時に、この星の海は不思議な魅力に満ちています。
ちなみに比較的新しい作品ですと、森見登美彦作『ペンギン・ハイウェイ』や藤田和日郎作『双亡亭壊すべし』は本作の影響を受けて書かれているとのこと。そちらの作品のファンのみなさんも、ぜひ一度『ソラリス』を手に取ってみてください。今までとは違った視点で作品を楽しめるようになるかもしれませんよ。