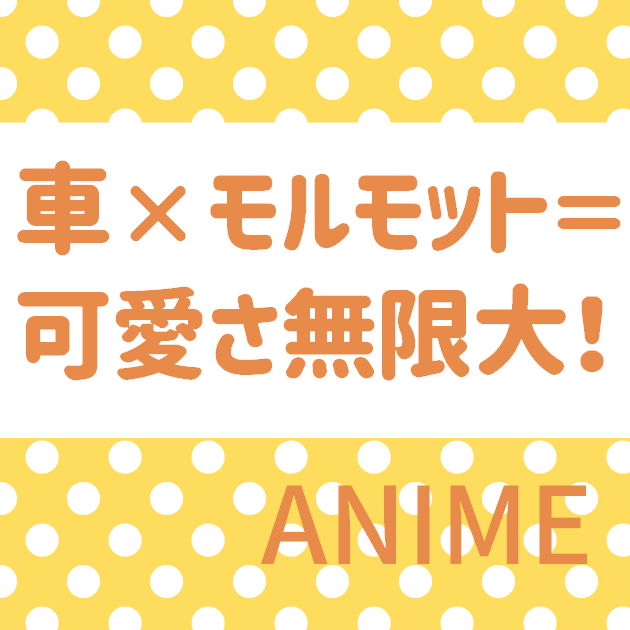『ピーター・パンとウェンディ』(原題:Peter and Wendy)は、ジェームズ・M・バリーが自身の戯曲を小説化した作品です。
なお、本作の前身となる小説『小さな白い鳥』(The Little White Bird)や『ケンジントン公園のピーター・パン』(Peter Pan in Kensington Gardens)にも同名の男の子が登場しますが、そちらのストーリー・設定は本作とは異なるものとなっています。
あらすじ
たくさんの不思議と冒険に満ちた世界、ネバーランド。ダーリング家の三姉弟ウェンディ・ジョン・マイケルは、しばしば夢の中でこの島を訪れては楽しんでいました。
ところがある夜、ネバーランドのヒーロー、ピーター・パンがに本当に目の前に現れ……。
メインキャラクター
ウェンディ
何事もきちんとしていることを好む少女。迷子たちのお母さん役として、弟のジョン、マイケルとともにネバーランドに迎え入れられます。
ダーリング夫妻、ナナ
心優しく美しい夫人は、子どもたちにおとぎ話を聞かせるのが上手。対する夫のダーリング氏は、金勘定や世間体ばかり気にしているタイプ。ナナは優秀な子守り犬です。
ピーター・パン
迷子たちのリーダー。行動力があって頼りになる一方、うぬぼれ屋で飽き性、忘れっぽいという困った面も。
ティンカー・ベル(ティンク)
鈴の音のような声をした妖精。ピーターと仲のいいウェンディに嫉妬するあまり、たいへんな事件を引き起こすことに……。
迷子たち(ロスト・ボーイズ)
乳母車から落ちた後、引き取り手が見つからないままネバーランドに送られた少年たち。現在は、トートルズ、ニブズ、スライトリー、カーリー、双子(個人名なし)の6人。
ジェームズ・フック
海賊船ジョリー・ロジャー号の船長。残忍な性格ですが、どことなく気品が感じられる人物。右手の代わりに鉄の鉤をつけています。
内容紹介と感想
実は怖い『ピーター・パン』
『白雪姫』『美女と野獣』など、ディズニーが映像化した古典的名作は、エンターテイメントとして完成度が高いものばかりで、世界中で長く親しまれてきました。
ただ、原作の内容を改変しているケースも多く、それゆえに原作を読むとギャップにびっくりしてしまう、ということもままあるのです。本作『ピーター・パン』も、そんな作品のひとつと言えるでしょう。
誘拐事件?
小説では、ところどころに怖さを感じる描写が見受けられます。
まず、ウェンディたちが両親の帰宅時にちゃんと家にいたのがディズニー版。
一方、長期間にわたってネバーランドに滞在しているのが原作です。子どもたちの失踪に関して、ダーリング夫妻やナナが「あの日、外出しなければ…」「いつも通りそばについていれば…」と後悔し、嘆き悲しむくだりがあるため、誘拐事件のような気がしてきます。
確かに、ネバーランドに行きたがったのはウェンディ自身です。しかし、彼女の興味を引くようなことを言って背中を押す、そんなずるさをピーターが見せたのもまた事実。
子どもの無邪気さと同時に、残酷さ・むごさを繰り返し描いているのが原作なのです。
両親やナナの心配をよそに、子どもたちに反省の色はありません。ウェンディは、お母さんは必ず窓を開けて待っていてくれるはず、とのん気に構えています(実際、その通りではあるのですが)。最年少のマイケルに至っては、ネバーランドにいるうちに両親の記憶をほとんど忘れかけてしまいます。
迷子たちのその後
血なまぐさい話ですが、迷子たちは戦闘で命を落とすことがあるようです。
また、彼らの間では大人になるのはルール違反であるため、迷子たちが大人になりそうになると、ピーターに間引かれてしまいます。これが何でもないことのようにさらっと書かれているあたりが、ものすごく怖い。
ちなみに、ピーターには他の迷子たちとは明らかに違う点があります。それは、遊びとしての食事はできるものの、お腹を満たすために、本当の意味で食べることはできない、などです。こうした特徴から、彼自身は乳歯のままの子どもでいられるのかもしれませんね。
そんな彼ですから、その日の気分によって周囲にも食事のふりだけで済ませるように強要することもあるわけです。他にも、自分と同じ服装をすることを禁止したりするなど、ピーターは時に暴君めいた態度をとります。
もっとも迷子たちは迷子たちで、目新しい話(ダーリング家に行くこと)につられた際は、ピーターが来なくても別に構わないという、幼い子どもならではの薄情さを見せつけるのですが。仲間同士の絆は一体どこに……?
ワニとの因縁
フック船長はある一匹のワニを恐れています。「強い海賊である彼がなぜ?」と思うでしょうが、もとをただせば、それはピーターが切り落としたフックの手を通りすがりのワニにあげてしまったからなのです。味を占めたそのワニは、フックをつけねらうようになりました。
今はワニが飲み込んだ時計の音のおかげで接近を察知できますが、もしその時計が止まってしまったら、と不安がるフック。悪人と言えど、この経緯にはさすがに同情してしまいます。
ピーターという子どもとフックという大人
あれこれ書きましたが、ピンチの時にウェンディを優先して逃がしてあげるところなどは、やはりかっこいいピーター・パン。今にも水没しそうな入江で恐怖を覚えたのもほんの一瞬。「死ぬことって、ものすごい大冒険だぞ」と、すぐに切り替えのできる、とんでもない感性の持ち主です。
そんなピーターのライバルにあたるのがフック船長。ディズニー版ではコミカルな役回りをすることも多い彼ですが、原作者にとって思い入れが強いキャラクターなのか、小説では非常に丁寧に描写されている印象を受けます。
チャールズ2世を思わせる容姿で元々は端正な顔立ちをしている、実は上流階級の出身で有名なパブリック・スクールに在籍していた、礼儀作法にこだわりがあり、無骨な海賊仲間の中で孤独を抱えている……。ピーターの生い立ちに関する背景がはっきりしないのに比べると、設定盛りだくさんです。
「パン、きさまは誰なのだ、何者なのだ?」フックはしゃがれ声でききました。
(大久保寛訳『ピーター・パンとウェンディ』新潮文庫より)
「若さだ、喜びだ」ピーターは思いつきで答えました。「卵から出てきた小さな鳥だ」
もちろん、こんなのは無意味な言葉でした。しかし、不幸なフックには、はっきりわかりました──ピーターが自分が誰でどんな者なのか少しもわかっていない、ということが。そして、それこそが礼儀作法の極みなのです。
フックの言う「何者」とは、要は家系についてであるとか、どこの学校を出ているかとか、そういったことでしょう。いかにも大人が気にしそうなことです。
ピーターは、両親が「この子は大人になったら何になるだろう」と話しているのを聞いて、生まれてすぐに逃げ出したといいます。だって、いつまでも子どもでいたいから。心理学者ダン・カイリーが提唱した「ピーターパン症候群」(Peter Pan Syndrome)の由来ですね。
永遠の子どもは、ただの「子ども」以外の何者でもないのかもしれません。
子ども時代の終わり
大人になってから本作を読むと、胸に迫るものがあるのが最終章。当初はなかった加筆部分です。
ようやく帰宅したウェンディは、ダーリング夫人から許可をもらい、その後も年に一度、春の大掃除の間だけはネバーランドで過ごしてもよいことになります。
1年後、約束通りダーリング家を訪れてくれたものの、ピーターは古い冒険のことをすっかり忘れていました。ウェンディがフック船長やティンカー・ベルの話題を出すと、まさかの「誰それ?」という反応。
「今度こそフックかぼくかだ」とまで思い詰めて挑んだ決闘は何だったのでしょう? ティンクが命がけでピーターを助けた、あの感動の場面は? ウェンディと同じく、私もショックを受けてしまいました。
ピーターには時間感覚がまるでないのです。彼が次に迎えに来てくれたのは2年後、さらにその次の再会は、なんとウェンディが大人になってからでした。
信じる心を失くし、空を飛べなくなった元子どもたち。今や男の子たちは普通の勤め人、ウェンディは結婚して一児のお母さんです。
「どうしてもう飛べないの、お母さん?」
(大久保寛訳『ピーター・パンとウェンディ』新潮文庫より)
「大人になったからよ。人は大人になると、飛び方を忘れてしまうの」
「どうして飛び方を忘れてしまうの?」
「もう陽気でも無邪気でも情け知らずでもなくなるからよ。飛べるのは、陽気で無邪気で情け知らずな人だけなの」
ウェンディにはもうできないことが、娘のジェーンにはいとも簡単にできてしまいます。そして、陽気で無邪気で情け知らずな子どもは、ピーターと一緒に空を飛んで行ってしまうのです。親の心子知らず、とはこのことですね。
ピーター・パンはいつだって「今」を生きています。時々悪夢にうなされることはあるようですが、基本的には過去を悔やむこともなければ、未来を憂えることもないのでしょう。
おわりに
今回の記事では触れずじまいでしたが、本作は、地下の家でのにぎやかな生活、人魚の入江での水遊び、タイガー・リリー救出といった、魅力的な冒険譚には事欠かない作品です。やはり原作を存分に味わうには、実際に手に取って読んでいただくのが一番であると思います。
大人になることを拒絶した男の子ピーターと、いずれ大人にならなければいけないことを自覚している女の子ウェンディ。大人になったウェンディには、泣いているピーターの慰め方がもはやわかりません。
本人が望んで選んだ道ではありますが、「おかえりなさい」と言って親が抱きしめてくれる喜びを知らない、友人たちとともに成長できない、そんなピーター・パンという存在には、どこかもの悲しさがつきまといます。