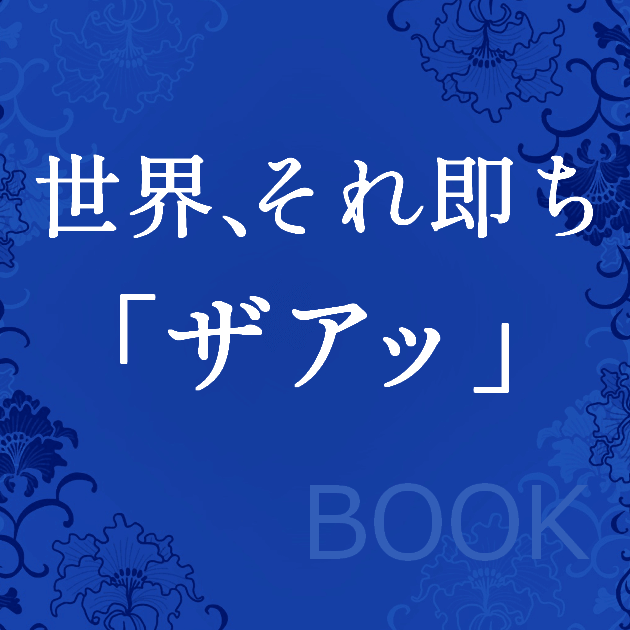あらすじ
ずっと昔、ある人から次のような奇妙な話を聞いたことがある。それは、その人の友人の体験談であった。
何でも「大器晩成先生」と呼ばれる苦学生が、ある時原因不明の病にかかり、療養がてら地方を転々としていたのだそうだ。
道中、無類の霊泉とされる滝の噂を聞いた晩成先生は、その滝がある奥州の古寺へ足を運んだらしいのだが……。
内容紹介と感想
大器晩成先生
貧しい家庭に生まれながらも、やっとの思いで上京し、高い志を持って大学に入った努力家──そんな彼に付いたあだ名が「大器晩成先生」。同級生より5~6歳も年上で、さらには苦労した分、言動も老け込んでいたんですね。
しかし、本人はそんなふうに言われても受け流し、いたって真面目に、そして大きな喜びを感じながら、勉学に励んでおりました。
そんなわけで、他の学生から遠巻きにされる一方で、尊敬の念を集めてもいたのです。
ちなみに、同級生のしている遊びは、地の文で「無邪気な、言い換れば低級でかつ無意味な飲食の交際や、活溌な、言い換れば青年的勇気の漏洩に過ぎぬ運動遊戯の交際」などと揶揄されています。うーん、なかなか手厳しいコメント。
本作の序盤を読んでいると、無為に過ごした自分の学生時代が思い出され、反省しきり。この時点では、私も晩成先生のことをただただ立派だと思っていたのですが……。
3人の僧侶
山奥が舞台である・登場人物に僧侶がいる・幻想的な雰囲気を醸し出している、といった点で、本作と泉鏡花の『高野聖』は通じるところがあります。もっとも本作には『高野聖』のような美女は出てきませんが。
晩成先生が東北地方のとある貧乏寺で出会ったのは、若僧の蔵海、太った中年男で赤ら顔の和尚、もはや生死を超越しているかのような老僧の3人。
和尚の容貌に関しては「麦藁帽子を冠らせたら頂上で踊を踊りそうなビリケン頭」という独特の言い回しが秀逸。通天閣のビリケンさんがお坊さんの格好をしているところを想像すると、ちょっと笑えますね。
この僧侶たちは基本的に親切ですが、和尚が当初警戒心をあらわにしていたり、耳の聞こえない老僧がいつのまにか晩成先生の苗字を把握していたりと、ひっかかるポイントがないわけではありません。後者については、先生が考え直したように蔵海が手話で伝えただけ、という解釈もできますが。
こんな調子で、見ようによっては不思議なような、何の不思議もないような、そんな話がずっと続きます。
そして3人もお坊さんがいるのだから、誰かが晩成先生に諭すようなことを言う場面があるのかと思いきや、特にそんなこともないという……。
降りしきる雨
雨の描写が非常に印象的な本作。季節は秋の頃で、ひんやりとした空気が伝わってくるかのようです。
晩成先生が寺を訪ねた直後、蔵海が登場する前後では、「サアッと雨が降っている」という表現が4回も繰り返されます。がらんとした空間で待たされて、そこに雨音だけが響いていると、世界には自分一人しかいないような心細い気持ちになりそうです。
私は雨の日に明るくて暖かい室内にいると、ほっとして心地よい気分になることがあるタイプなのですが、夕闇迫る見知らぬ山寺というシチュエーションではさすがに耐えられない。怖くて風流を楽しむどころではありません。
先生の寂しさも募るばかりで、「雨の音ばかりザアッとして、空虚に近い晩成先生の心を一ぱいに埋め尽くし」、横になっていると次のような考えまで浮かんできました。
雨は恐ろしく降っている。(中略)自分の生涯の中の或日に雨が降っているのではなくて、常住不断の雨が降り通している中に自分の短い生涯がちょっと挿まれているものででもあるように降っている。(中略)世界という者は広大なものだと日頃は思っていたが、今はどうだ、世界はただこれ
ザアッ
というものに過ぎないと思ったり、また思い反して、このザアッというのが即ちこれ世界なのだナと思ったり(後略)
あらゆる音がこの「ザアッ」に内包されているような気がしてきた晩成先生。
すなわち、世界のすべては渾然一体となって存在しているということ……? これはある意味、この世の真理でしょうか。
橋流れて水流れず
タイトルにもなっている絵画は、物語終盤になってようやく登場します。
真夜中、蔵海と和尚に起こされた晩成先生は、洪水に備えて念のために小高い場所にある草庵(老僧のいる隠居所)に避難することになりました。その奥の部屋で目にしたのが「橋流水不流」(橋流れて水流れず)と書かれた額と、壁一面を占めるほど大きな古い絵です。
調べたところによると、額の文字は禅の思想を示すものらしく、中国南北朝時代の人物、傅大士(善慧大士)の「法身の偈」という詩の一部のようですね。
周囲の自然と自分が一体化している、無心・無我の境地を表しているのだとか。雨音を聞きながら晩成先生があれこれ考えた内容がこの「橋流水不流」という一言に集約されているようです。
画を観る
絵は風俗画で、大河に面した都の風景が描かれていました。そこには市井の人々の日常があり、晩成先生は特に船頭のおじいさんの姿に心を惹かれます。
その様子は「何ともいえない無邪気なもので、寒山か拾得の叔父さんにでも当る者に無学文盲のこの男があったのではあるまいかと思われた」。
寒山と拾得というのは、夏目漱石の『夢十夜』の記事(第六夜)でもちらりと触れましたが、中国の唐の時代にいたとされる伝説的な詩僧のことです。
寒山はボロボロの服を着て洞窟に住み、友人の拾得に残飯を分けてもらったり、また問題行動を注意されると二人して笑いながら走り去ったりと、奇行が目立つ人物であったとされます。
一方で、その脱俗的な暮らしぶりを風狂(※)とみる向きもあり、寒山と拾得は後世の禅僧の間で好んで用いられるモチーフとなりました。絵で描かれる場合は、お坊さんらしからぬボサボサ頭にニコニコ顔のことが多いようです。
※特に禅宗において、規格外の行動をむしろ悟りの境地にあるものとして肯定的にとらえようとする言葉。
この寒山・拾得の親戚のような船頭が人を呼んでいるさまを眺めているうちに、晩成先生も思わずにっこり笑って返事をしたくなってきました。
岩波文庫『幻談・観画談』の川村二郎氏の解説を参考にさせていただくと、このとき、「古画の小宇宙」を前にして「旅人はもはやただの観る人ではなく、画中の人物にひとしくなっている」。
この間、雨音についての記述が途切れていることからすると、晩成先生は外の大雨のことを忘れるほど絵に夢中になっていたのでしょう。
その後
晩成先生のその後については簡単に語られるのみです。
病気(精神的なものであった可能性も)は完治したものの、大学には戻らずじまい。平凡に生きていくことを決めたようで、農業に従事しているのを見かけた人がいるとか。
大噐不成なのか、大噐既成なのか、そんな事は先生の問題ではなくなったのであろう。
この一文で物語は締められます。
大企業で出世するとか、学者として有名になるとか、そういった社会的成功が晩成先生の中で無価値になった……というのとは少し違うのかな、と私は思いました。ただ、そのような世間一般が考える名誉を特別視することがなくなったということかなあ、と。
学問で身を立てようとしていた生真面目な晩成先生が、無学で無邪気な船頭のおじいさんに好感を持ったということは、つまりそういうことだったのではないでしょうか。
おわりに
現代ではなじみの薄い単語などが難しく感じられる箇所はあったものの、全体的には読みやすい文章でした。
また、作中に登場するモチーフについて調べていくと禅の精神がベースにあるようにも思われますが、晩成先生自身がそうだったように、禅について知らなくても本作を楽しむうえで何の支障もありません。
先入観で難解なイメージを持たずに、まずはまっさらな気持ちで名文を味わってみてはいかがでしょう。